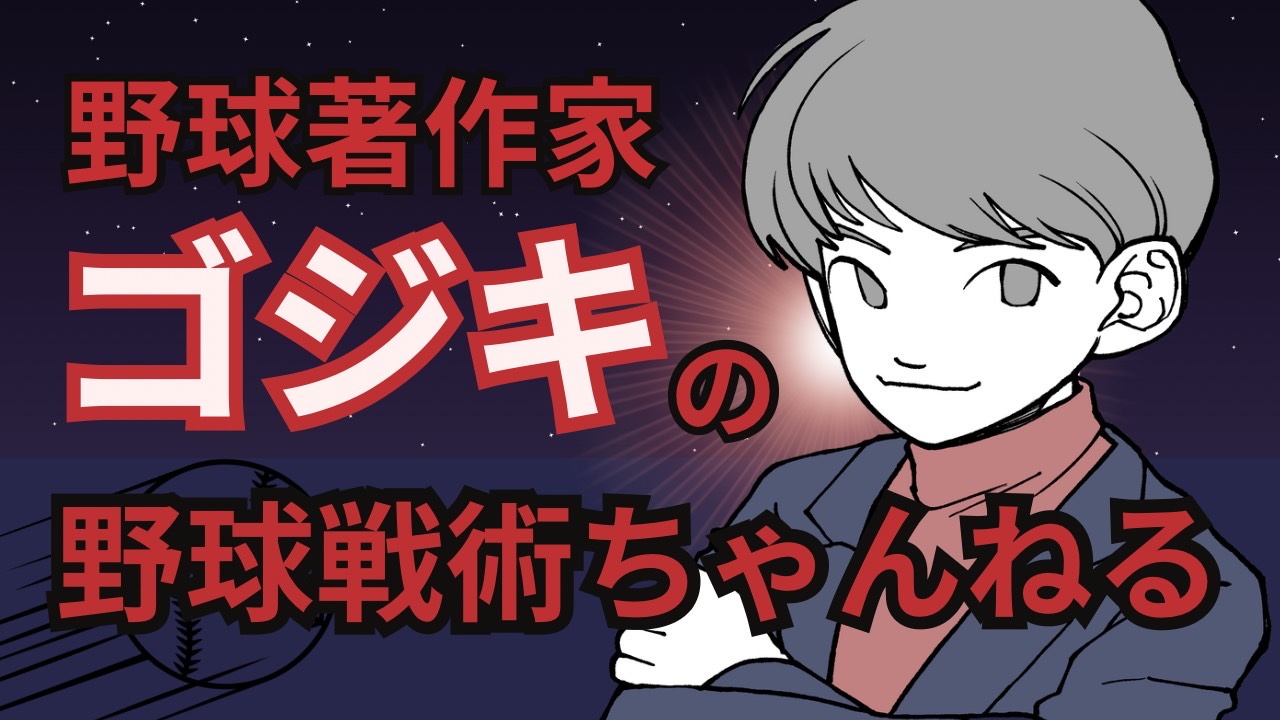小林誠司は“第3捕手”ではない! リード、ブロッキング、スローイング、そして状況判断はトップクラス──巨人の屋台骨を支える「守備の要」

2025年、読売ジャイアンツの捕手陣は新たなフェーズへと突入している。昨年、岸田行倫が台頭しただけでなく、今年は甲斐拓也が加入したことで、それぞれが出場機会を伸ばしている。さらに、打力のある大城卓三は一塁と併用しながら出場している。
そうなると、甲斐が怪我で離脱した現在、小林誠司の立ち位置は一見「第3捕手」に映るかもしれない。
だが、その実態はまるで違う。彼はただのバックアップ要員ではない。守備の要として、ベンチで、ブルペンで、そして必要なときにはマスクをかぶって、巨人の屋台骨を静かに支えている。
目に見える数字で測れない「守備力の本質」
小林は、打力には課題を抱えている。それは本人も、ファンも、首脳陣も理解している部分だ。
だが、守備に関しては12球団でもトップクラスと言っていい選手であることは、もはや疑いようがない。リード、ブロッキング、スローイング、そして状況判断……。この4要素すべてにおいて、小林は一流だ。
投手の特性を見極め、打者の癖を捉え、配球を構築する「読みの力」。パスボールやワンバウンドに対応する瞬発力と安心感。そして、状況ごとに守備位置やけん制をコントロールする判断能力。打撃成績には表れない“勝利のための技術”を、小林は一手に担ってきた。
実際、2024年シーズンの鉄壁のディフェンス陣の一員としてグラウンドに立っていたことも大きかったのは間違いない。
それでも、彼の守備力はしばしば正当に評価されない時期があった。マイルズ・マイコラスにマウンド上で激怒されたシーン。千賀滉大のフォークを捕球できなかったシーン……。一部のメディアが切り取った“失敗”の印象が、評価を下げる材料として流布された時期があったのだ。
しかし、そこだけを切り取るのはあまりに浅い。多くの投手が、実際の現場では高く評価してきた捕手である。特に長年バッテリーを組んだ菅野智之との関係は象徴的だ。
菅野のキャリアの中で最も圧巻のパフォーマンスを見せたのが2017年と2018年。この2年連続で沢村賞を獲得した裏側には、小林誠司のリードが存在していた。
剛球と制球を武器にする菅野が、より支配的な投球を見せられたのは、小林との意思疎通の精度が高かったからこそである。配球のクセやテンポを熟知した“女房役”の存在は、あのキャリアハイの裏に不可欠だった。
さらに、2024年も菅野の復活劇の裏には小林の存在が大きかったのは間違いない。また、2019年には山口俊が最多勝・最多奪三振・最高勝率の投手三冠を達成。この年、山口が登板した試合はすべて小林がマスクをかぶっていた。
つまり、2016年〜2019年の4年間で、小林がバッテリーを組んだ投手は、毎年のように先発投手部門のタイトルを獲得していたのである。
そして、彼のリードはピンチを脱する技術だけではない。崩れかけた投手を立て直す能力もあり、それが小林の真骨頂である。
投手のタイプに合わせた“細やかな仕掛け”
最近では、リリーフ投手とのバッテリーでも守備面の巧みさが光っている。例えば、若手投手とバッテリーを組んだ際、小林は「身体を大きく見せて構える」ことで、心理的な安心感を与える工夫を見せていた。
こうした対応力は、捕手のデータに表れにくい。フレーミング率や阻止率では測れない、“投手が最大限に力を発揮できる状況をつくる”職人芸だ。データだけでは判断できないからこそ、捕手というポジションは奥が深く、評価が難しい。
だからこそ、小林のような「見えない部分を支える守備型捕手」の価値は、知っている人間にこそ見えてくる。
小林が今、「第3捕手」として帯同している最大の理由は、その守備力だけではない。“教えられる捕手”としての資質に他ならない。
自身のリードを言語化し、若手捕手へ伝える……。試合中にはベンチで映像を見せながら「このタイミングで外すべきだった」「この打者の間は○○だ」と解説し、プレーに昇華させる。
ミーティングで話しきれなかった内容を補い、ブルペンでは投手の調整を横で見ながら、捕手との相性や球種の質を細かくチェックしている。
特に岸田行倫の台頭の裏には、小林の存在が欠かせなかった。あえて前に出過ぎず、だが常に「後ろから支えている」ような距離感。壁ではなく“橋”として若手と投手陣をつなぐ存在……。これが小林誠司の現在地である。
もちろん、チームとしては「打てる捕手」が重宝される傾向にある。それでも巨人が小林を一軍に帯同させるのは、“守れて勝てる捕手”という絶対的な価値があるからだ。
試合終盤、流れを止めたいときに小林をマスクに起用する。投手交代と同時に小林が入ることで、「試合が整う」瞬間がある。彼が配球の軸を再構築し、ミスを避け、淡々とゼロを積み上げる。“特別なことをしないことで、チームを勝たせる”それができる捕手は、極めて稀だ。
試合も終盤に差し掛かると、ベンチは静かに動き始める。投手交代とともにマスクが小林に渡されるとき、そこには明確な意図がある。
試合を冷静に判断したうえで進めたい……。守備のミスを防ぎたい……。配球に迷いが出ている……。
そんなとき、マウンド上の投手は小林の構えを見て安心する。投げるべきボールが明確になる。無理をしなくても、しっかりと勝負できる。その“空気”を整える力こそが、小林誠司が「守備の要」である最大の証だ。
今季も、巨人の捕手陣の中でのスタメン出場は減るかもしれない。だが、小林の存在価値は微塵も揺らがない。
彼は第3捕手ではない。打撃成績で測れない“守備の本質”を体現する存在であり、ベンチにいながらも試合を動かせる、「守備の要」としてチームの核にいる。
若手を支え、投手を導き、試合の流れを整える。それは、スタンドからは見えないかもしれない。だが、グラウンド上では確かに感じられる。
静かに、だが確実に勝利の構造を形づくる小林は、今もなお巨人に不可欠な存在である。
(文=ゴジキ)