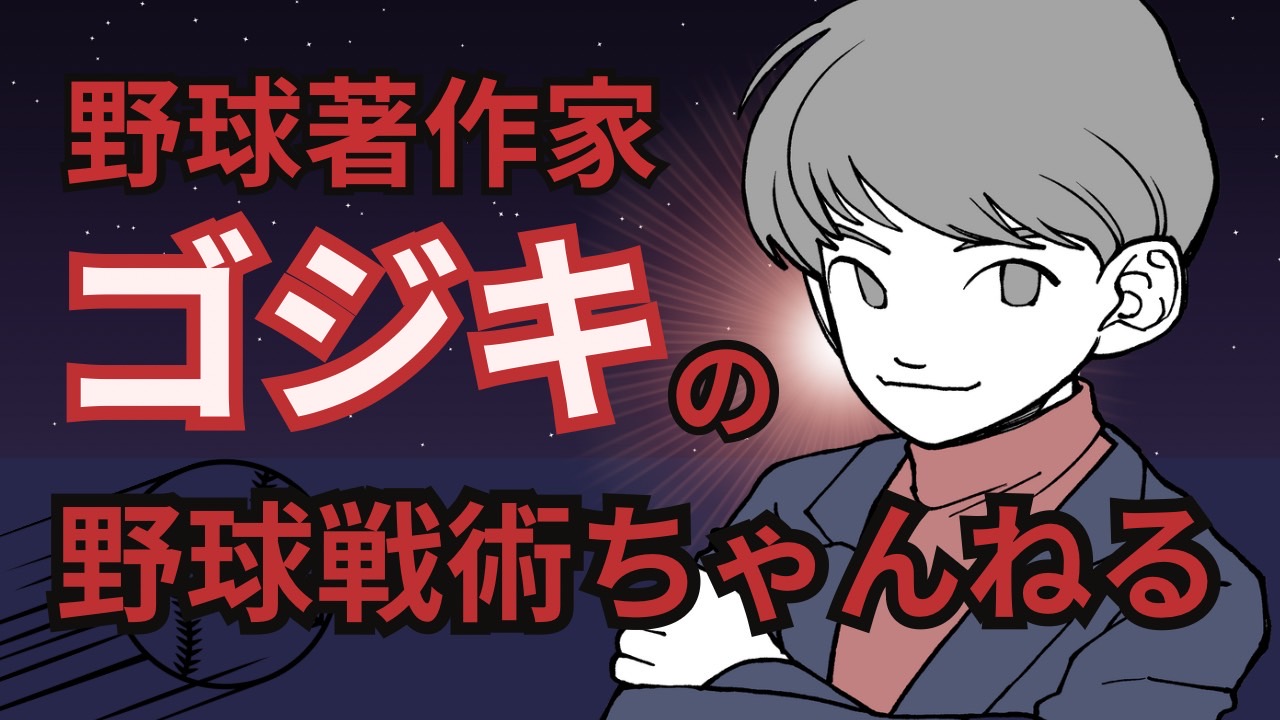坂本誠志郎と若月健矢の守備力……森友哉と坂倉将吾の攻撃力が示す分水嶺──攻守を融合する「統合型捕手」

捕手は長らく「守りの要」として評価されてきた。
リード、捕球、ブロッキング、そして投手との信頼構築。いずれもチームの根幹を支える作業であり、1試合に最も多くの球を受け、全プレーに関与する唯一のポジションといえる。
その役割は単なる守備者ではなく、戦略の立役者であり、心理戦の指揮官でもある。
坂本・若月らが築く“守りの壁”
試合のテンポ、配球の意図、相手打者の癖、投手の状態などを瞬時に読み取りながら、最適解を導き出す。それが、捕手が試合の空気を握るといわれるゆえんである。
しかし、その重要性ゆえに、肉体的・精神的負担は全ポジション中でも群を抜いて大きい。毎試合しゃがみ続け、ブルペンでの準備も欠かさず、気温や疲労に左右されながらも正確な判断が求められる。
この過酷なポジションをひとりで戦い抜くことは現実的ではなく、守備型と打撃型、あるいは経験値の高い捕手と若手捕手の併用が定着してきた。チーム全体で「捕手力」を分担し、戦略的にマネジメントする時代に移り変わっている。
坂本誠志郎(阪神)と若月健矢(オリックス)……。彼らはまさに、現代野球における捕手の基準点だ。
坂本は梅野隆太郎との併用で、持ち前の配球で投手陣の強みを最大限に引き出す捕手として存在感を放つ。若月は捕球技術と投手との信頼関係構築に長け、チーム防御率を支える象徴的な存在となっている。
彼らの強みは、数字に表れにくい部分にある。たとえば、リードによって被本塁打を抑え、試合展開を安定させる。ブロッキングで暴投を防ぎ、進塁阻止で流れを断ち切る。守備で失点を減らすことは、チーム全体の勝率を地道に押し上げる行為だ。まさに“壁”を築くタイプであり、捕手という職人の価値を再確認させる存在だといえる。
ただし、その“壁”を守るだけでは勝ちきれない現実もある。守備でマイナスをつくらないことが最低限の基準になった今、そこに「打撃でプラスを生む力」をどう加えるか……ここが現代野球における捕手の分水嶺となっている。
坂倉・森の系譜が切り拓いた“攻める捕手”
現役選手のキャリアを振り返ると、森友哉(オリックス)や坂倉将吾(広島)は、その分水嶺を飛び越えた“打てる捕手”の代表格だ。
彼らは単に打率が高いというレベルではなく、「チームの得点源」として戦略上の価値を持つ。捕手が上位〜中軸に座れるチームは、打線全体の厚みが増し、戦略の自由度が広がる。
一塁や三塁、外野に守備特化型を配置できる余白を生むことで、編成面でも利点がある。これは、森や坂倉が「打線を動かす捕手」として存在する意義を如実に示している。
また、大城卓三(巨人)のように、捕手+一塁の併用で出場機会を増やす起用も一般化してきた。
この場合、休養日でも打席を落とさず、チームの得点力を維持できる。代打・代走・守備固めのカードを温存できる点も、シーズンを通して大きなアドバンテージとなる。つまり、“捕手が打てる”という要素は、チーム戦略全体に波及する「乗数効果」を持つのだ。
攻撃面で相手バッテリーにプレッシャーをかければ、終盤の采配も変わる。捕手を代打に送る必要がなくなることで、控えの使い方が柔軟になり、勝負どころでの選択肢が広がる。これは「攻める捕手」がチームにもたらす最大の価値といえる。
とはいえ、打てる捕手がフルシーズン中軸を担うことには大きなリスクがある。打席数が増えることで疲労が蓄積し、夏場以降にパフォーマンスが低下するケースは珍しくない。捕手は試合中の動作量が圧倒的に多く、試合外でもブルペンや配球研究などで常に頭を使うポジションだ。肉体的・精神的疲労が翌年の成績低下につながることも多い。
このため、多くのチームが「2人、あるいは3人体制」の捕手運用を採用している。守備型・打撃型・経験型を組み合わせ、1シーズンをトータルで設計するのだ。
役割を明確にし、日程や投手との相性に応じて柔軟に使い分ける。捕手を「ひとりの職人」ではなく「ユニット」としてマネジメントする発想が、すでに主流となっている。
結局のところ、捕手というポジションは今、最も多面的な価値を問われている。守備だけでも、打撃だけでも足りない。投手を導きながら、打線の歯車にもなり、チームの勝ち筋を模索できるか……。それが次世代捕手の評価基準になる。
坂本や若月が築いた堅牢な基準、森や坂倉が提示した攻撃的潮流。その2つをどう融合させるか。守備と攻撃のバランスを取りながら、チーム全体の機能性を最適化する……。この「統合型捕手」の時代が、すでに始まっている。
(文=ゴジキ)