新たな「レア・グルーヴ」を求めて日本へ…シティポップの次は高中正義・T-SQUARE・カシオペア? 日本のフュージョンが海外で人気上昇の理由

アナログレコード専門店「Face Records」のニューヨーク店「Face Records NYC」が発表した2025年上半期の「邦楽レコード売れ筋ランキング」を発表。
それによると、日本の「フュージョン」がアメリカの若者たちの間で人気を集めているという。
高中正義やカシオペアといった1970年代後半から80年代後半に活躍したアーティストたちが、再び注目を浴びているのだ。
T-SQUAREに惹かれ、日本へ留学した若者も
「カルロス・サンタナの動画をYouTubeで見ているうちに、関連動画で高中正義に出会ったんです。そこからサディスティック・ミカ・バンドや渡辺香津美も聴くようになりました。高中のギターはどこかエキゾチックで、日本のフュージョンにはアメリカの音楽にはない独特の華やかさがあります」
そう語るのは、都内のレコードショップでアナログレコードを物色していた、日本在住のアメリカ人男性(32歳)。
80年代に活躍したファンクバンド・スペクトラムの「F・L・Y」がTikTokでバイラルヒットしたように、近年は日本のフュージョンが海外で人気を博している。それも、若者の間でだ。昭和音楽大学に通う日本在住の中国人男性(26歳)はこう語る。
「僕はT-SQUAREに衝撃を受けて、日本で音楽を学びたいと思うようになりました。彼らの演奏には心を揺さぶられる力があります」
そもそも、フュージョンとは、ジャズにロックやラテンなどを掛け合わせた「クロスオーバー」な音楽ジャンル。日本では1970年代後半から80年代後半にかけてブームとなり、高中正義、カシオペア、T-SQUAREといった実力派がジャンルをけん引した。
ただ、このジャンルは“玄人”の間では人気が高いものの、一般的なイメージは「ショッピングセンターのBGM」あるいは「F1のテーマ曲」である。つまり、「ちょっとダサい」という印象が持たれている。
それが今や、シティポップの次に海外人気に火がついているという。一体何が起きているのだろうか?
この世界的ヒットの背景について、『ポップミュージックはリバイバルをくりかえす 「再文脈化」の音楽受容史』(イースト・プレス)などの著作がある評論家/音楽ディレクターの柴崎祐二氏に話を聞いた。
リアルタイムで海外人気があった日本のフュージョン
――近年、海外では日本のフュージョンブームが訪れています。
柴崎祐二(以下、柴崎) 例えばYOASOBIのようなメインストリームに食い込む人気と比べると、フュージョン人気はサブカルチャー的な広がりにとどまっていると思います。ただ、「シティポップ」のリバイバルがピークだった頃に比べれば規模はやや小さいものの、その流れを引き継ぐかたちで、フュージョンにも関心が集まり始めている印象があります。
――海外での日本のフュージョン人気は、いつ頃から始まったのでしょうか?
柴崎 元をたどれば、1970年代末、ロンドンを中心としたクラブシーンでは、ジャズやフュージョンで踊る「ジャズダンス」と呼ばれるムーブメントがありました。当時は、アメリカ産のジャズ・ファンクやフュージョンが主にプレイされていたのですが、ある時期から、マニアックなレコードディーラーたちが、日本からレコードを輸入するようになるんです。しかもそれを、リアルタイムでジャズダンスの現場で流していた。その結果、渡辺貞夫さんや日野皓正さんといった大御所の作品をはじめ、さまざまな日本のレコードが少量ながら出回り、DJたちの間で日本のフュージョンが非常に高く評価されるという現象が起きていました。
――最近の流行かと思いきや、そんな昔から受容されていたんですね。
柴崎 例えば、カシオペアは日本では腕利きミュージシャンによる「オーバーグラウンドなバンド」というイメージがあるかもしれません。しかし、イギリスのクラブシーンではサブカルチャー的な存在として人気を博していました。実際、1980年代前半にカシオペアがロンドンでライブを行ったときには、ジャズダンス・シーンのDJやダンサーたちが集まって、大盛り上がりだったという話があります。つまり、現在のフュージョン人気の下地は、その頃からすでに存在していたんです。
――海外進出や「逆輸入」といえば、YMOのイメージが強いですが、その後はフュージョンバンドが進出していったのですね。
柴崎 ちなみに、カシオペアは昔から、東南アジアでも人気があります。その理由は、80年代当時から欧米だけでなく東南アジアにもツアーで回っていたからなんです。やはり、インストゥルメンタルは言語の壁がないというのが大きいですよね。
シティポップブームと「レア・グルーヴ」
――フュージョンの前に、シティポップが世界的に注目されていました。これは一体、何だったのでしょうか?
柴崎 まず、アニメやゲームを通して、日本文化がミレニアル世代以降にとって非常に身近な存在になっていたという背景があります。その中で、J-POPを深く聴くようなコアなコミュニティもすでに存在していましたが、もうひとつネット発のアンダーグラウンドな流れとして、「ヴェイパーウェイヴ(Vaporwave)」というジャンルが登場しました。
――これはYouTubeで流行した、80〜90年代の消費社会的な映像や音楽を、あえてチープに加工してネット上で再構築するような表現スタイルですね。一部の音楽マニアやネット文化が好きなものたちの間で人気を博しました。
柴崎 そこから、「フューチャーファンク(FUTURE FUNK)」という、よりダンスミュージック的なサウンドのサブジャンルが派生し、そこでシティポップの楽曲が頻繁にサンプリングされるようになりました。実はこの時点で、すでにフュージョンの楽曲も使われていたんです。こうした動きと並行して、元ネタ曲に注目が集まっていったのと、当時のYouTubeのアルゴリズムに基づいて、めったやたらに竹内まりやの「プラスティック・ラブ」がレコメンドされる、といった現象も起きていました。
――シティポップブームを代表する楽曲ですね。
柴崎 それによって、一部のマニア以外にも認知され、ネット上でのバズに繋がっていきました。さらに追い風となったのが、TikTokのようなショート動画プラットフォームの普及です。大貫妙子さんの「4:00 A.M.」や、松原みきさんの「真夜中のドア〜Stay With Me」などは、そう言ったショート動画のBGMとして使われたことでさらに大きく注目されました。そして、それをきっかけに海外のYouTuberがカバー動画を投稿するなど、バイラル的に広がっていきました。
――なるほど。そこから、『YOUは何しに日本へ?』(テレビ東京系)で、大貫妙子さんの『SUNSHOWER』を探しに来日したYOUにつながるわけですね。
柴崎 あのYOU――スティーブさんは、今話したような文脈とは少し異なるのではないかと思います。時系列的にも、TikTokなどで大貫妙子さんの曲が話題になる前ですね。実は、海外では1970年代後半の日本のレコードが「レア・グルーヴ」の一種として1990年代から注目されていた歴史があるんです。当時の彼の発言などからすると、どちらかというとそういう受容の流れの中でレコードを探しにきたという理解が近い気がします。
――レア・グルーヴというのは、現代ではあまり顧みられる機会は少ないけれどクラブ・ミュージックの目線で質の高い音楽を“発掘”するように楽しむジャンルです。
柴崎 そうです。そして、すでに90年代には、例えば山下達郎さんや吉田美奈子さんといったアーティストのレコードが、一部の海外のDJの間で高く評価され、人気を集めていました。
――フュージョン同様、その頃からすでにシティポップは、マニアの間では聴かれていたのですね。
柴崎 近年のシティポップの盛り上がりは、こうした複数の文脈が入り混じった結果だと思います。2010年代の終わりに、それらが一気に融合し、現在に続くような状況が生まれたんです。詳しくは僕が編著を担当した本にも書いてあるので、ぜひ読んでみてください(笑)。
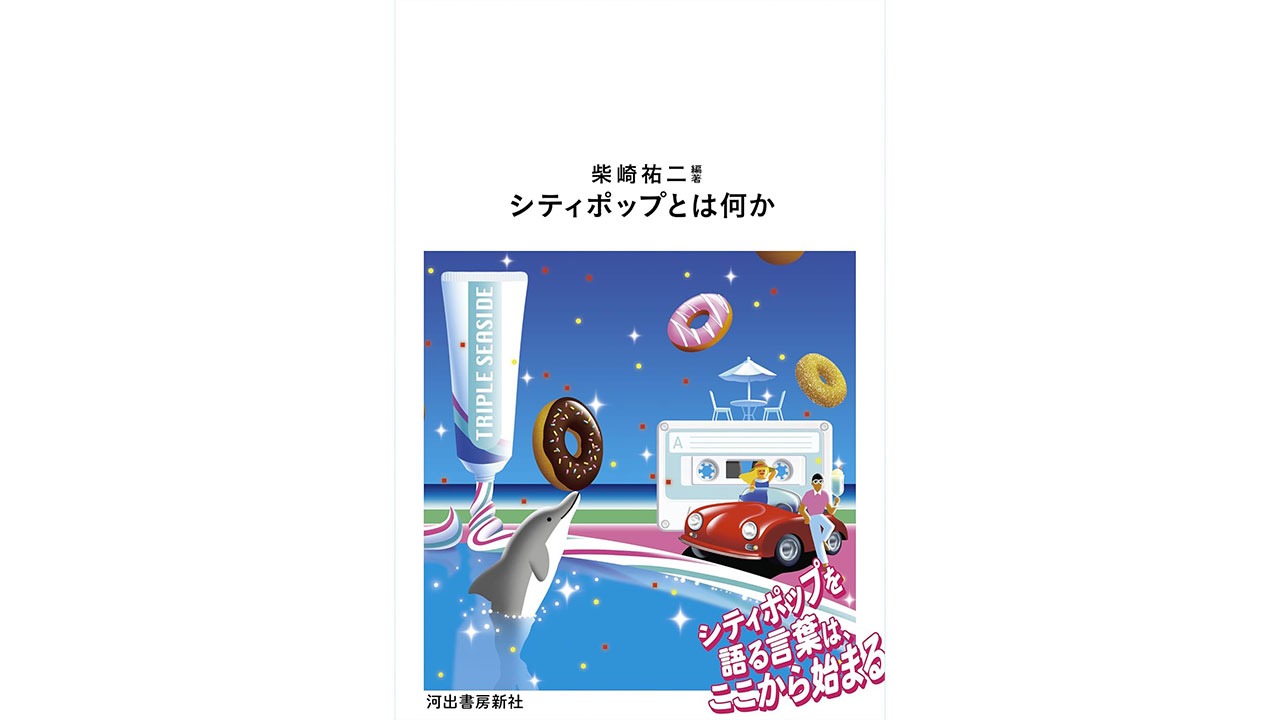
作業用BGMとして若者たちに火がついた!?
――シティポップの楽曲にはフュージョン系のアーティストも参加していたため、シティポップからフュージョンへと、リスナーはシームレスにつながっていったのかもしれません。
柴崎 そうですね。なぜネットを中心に日本のフュージョン人気が広がったのかというと、「作業BGM」文化との親和性が非常に高いからだと思っています。シティポップもYouTube上では、BGM的に聴かれていた部分も大きかったと思います。
――YouTubeの「作業BGM」といえば、窓辺で勉強している女の子のアニメーションとともに、ローファイヒップホップが24時間365日配信されている「Lofi Girl」が代表的ですね。
柴崎 流しっぱなしにしても邪魔にならない音楽ということで、シティポップを聴いていると、関連動画で日本のフュージョンが表示されるようになりますよね。YouTubeの自動再生機能もブームの背景として重要な要素だと考えています。
――YouTube上には、当時の日本のアルバムがフルで違法アップロードされていたりしますね。
柴崎 もちろん、著作権法上の問題を無視することが出来ませんが、ある程度長い時間変わらないムードに浸れるというのも魅力だったのだろうと思います。そこに加えて、高中正義さんの人気には、もちろんサウンドの魅力もありますが、ジャケットのキャッチーさも大きな要因だったと考えています。たとえば『All Of Me』では高中さんがスカイダイビングで空から落ちていたり、『AN INSATIABLE HIGH』では一本道を走っていたりと、サムネイルとして視覚的なインパクトが強いんです。
――確かに。どこかユーモラスですよね。
柴崎 また、高中さんと同時期に活躍していた菊池ひみこさんの『Flying Beagle』というアルバムもあります。ジャケットにはビーグル犬が大きく写っているのですが、英語圏のリスナーからすれば「空飛ぶクルマ(flying vehicle)」ではなく、「空飛ぶビーグル犬?」という言葉遊び的な面白さを感じるでしょう。いってみれば、ネットミーム的なフックがある。あのかわいいジャケットで、実際のサウンドはバキバキにカッコいい演奏なわけですから、それは心惹かれますよね(笑)。
――「いい意味で裏切られた!」と感じる人も多そうですね。
柴崎 シティポップの人気も、竹内まりやさんの「プラスティック・ラブ」のサムネイルがキャッチーだったというのも一因だったと思います。
――なるほど。音楽性だけではなく、多角的な要素が重なって、フュージョン人気が形成されたんですね。
柴崎 そして、それはネットの中だけで完結せず、現実世界にも波及していて、レコード店でも軒並み人気アイテム化している。今、高騰しているアナログレコードを見ると、どれもアイコン性が高いんですよ。例えばカシオペアのアルバム『MINT JAMS』はYouTubeで678万回再生されていますが、ジャケットも非常に洒脱でキャッチーです。
――ミントジャムの瓶をあしらった、スクリーントーンのようなイラストが特徴的ですよね。帯付きだと中古でも1万円を超えています。
柴崎 高騰の背景には、サウンドとしてのフュージョン人気だけでなく、アナログレコードのジャケットをSNSに投稿したり、部屋に飾るといいった、ライト層を巻き込んだ「レコードブーム」の存在もあるでしょう。実際、レコード店に「『MINT JAMS』はありませんか?」という問い合わせが多数寄せられた時期もあったそうです。
実はフュージョンとテレビゲームとの関連性も!?
――「サンダーキャットも日本のフュージョンが好き……。つまり、昔から日本の音楽はすごかったんだ!」と思いたくなりますが、実はインターネットを介した人気の側面も大きかったのですね。
柴崎 そうですね。例えば、YouTubeで「Japanese Fusion」と検索すると、海外の人たちの解説動画がたくさん出てきます。そこでよく語られているのが、「テレビゲームのBGMみたい」という印象です。「自分たちが遊んでいたゲームのBGMは、実はフュージョンだったんだ」という気づきが、今起きているわけですね。例えば『スーパーマリオブラザーズ』の有名なテーマ曲と、T-SQUAREの「Sister Marian」の共通性を指摘する動画があったりします。
――面白いですね。
柴崎 それに、『グランツーリスモ』シリーズの音楽を初代T-SQUAREのリーダー安藤正容さんが手がけているなど、当時のゲーム音楽にはフュージョンやプログレ系のアーティストが多く関わっていました。
――スーパーマーケットだけでなく、オタク文化にもフュージョンが根付いていたんですね。
柴崎 特に一部海外ユーザーの間でそれらを結びつけて受容する傾向が顕著です。幼少期にゲームで聴いていた音楽の記憶に、フュージョンのイメージが重なるというわけです。これはかつてのヴェイパーウェイヴ的な感性にも近いですよね。
――フュージョンだけではなく、ブレイクビーツを早回しして生まれる高速で複雑なドラムが特徴の「ジャングル」も、かつてゲーム音楽に使われていた影響で、YouTubeでは「PlayStation Jungle Mix」などの動画が人気を集めています。
柴崎 そうですね。日本のフュージョンが海外で注目されている理由を掘り下げていくと、ノスタルジーもあるし、レア・グルーヴ文化との接点もある。いろんな文脈が交差していて、決して一過性のブームではないことがわかります。日本のフュージョンが誕生した時代からの連続性が、今につながっているのだと思います。
(取材・文=千駄木雄大)
柴崎祐二(しばさき・ゆうじ)
1983年、埼玉県生まれ。音楽ディレクター/評論家。2006年よりレコード業界でプロモーションや制作業務に従事し、多くのアーティストのA&Rを務める。著書に『ポップミュージックはリバイバルをくりかえす――「再文脈化」の音楽受容史』(イースト・プレス)、『ミュージック・ゴーズ・オン〜最新音楽生活考』(ミュージック・マガジン)。編著に『シティポップとは何か』(河出書房新社)などがある。
関連記事
「あなた、逮捕されてください!」 Amazonや楽天を一度でも利用すれば特殊詐欺の標的に!? 通販サイトの個人情報と“警察を名乗る詐欺”の意外な関係
潜入ライター・國友公司の“ワイルドサイド漂流記”──歌舞伎町、西成、モンゴル、インドで出会った強烈な人々
モモレンジャーの原型は“忍者モノ”にあった? 東映・名物プロデューサーが語る! 「スーパー戦隊シリーズ」に女性ヒーローが不可欠な理由
2人にひとりは借りる時代…奨学金返済問題に企業はどう対処する? 奨学金返還支援型人材紹介サービス「奨学金バンク」に訊く
2人にひとりは借りる時代…奨学金返済問題に企業はどう対処する? 代理返還制度を導入したPR TIMESに訊く
