北海道出身力士、外国人力士、モンゴル勢の影響…なぜ外国人力士は横綱になれなかったのか? 「相撲」を「経済学」で導き出す

年々高まる大相撲人気。その勢いは、平成の「若貴ブーム」に匹敵するとも言われている。そんな中、相撲に関する異色の本が1月に出版された。その名も『経済学で読み解く大相撲300年史:本所、そして両国の磁場』(日本評論社)だ。
相撲×経済学という組み合わせ自体が珍しいが、本書では相撲の歴史や文化、さらにはグローバル化に至るプロセスまで幅広く扱われており、経済に明るくない読者でも楽しめる作りになっている。
今回は、著者である西南学院大学経済学部教授の山村英司氏にインタビューを行い、本書の見どころや相撲への情熱、データ分析の面白さについて語ってもらった。
経済学から見た相撲界とは?
——相撲と経済学という、あまり見慣れない組み合わせですが、山村さんはそもそも相撲はお好きなのですか?
山村英司(以下、山村) 私は北海道出身で、子どもの頃から相撲は身近な存在でした。 というのも、北海道出身者が活躍する競技といえば、ウインタースポーツと相撲ですからね。特に私の幼少期には、横綱や大関に北海道出身者が多く、北の富士、千代の富士、北勝海といった力士たちの活躍を見て育ちました。
——郷土のスターたちが勢揃いだったのですね。
山村 しかし、本を書く直接のきっかけとなったのは、福岡の西南学院大学に赴任したことです。九州場所の時期になると、街で浴衣姿の力士を見かけることも多く、家の近所には相撲部屋の宿舎がありました。それらを目にするうちに、相撲への興味が再燃したのです。それに、20年ほど前には、ゼミの生徒たちと中村部屋の稽古を見学したこともありました。
——20年くらい前というと、現在の中村部屋とは系譜が異なる、高砂一門の旧・中村部屋でしょうか。いったいなんのために見学を?
山村 時期的には、元関脇・富士櫻が親方を務めていた頃ですね。当時、部屋のおかみさんだった中澤嗣子さんが『相撲部屋24時 おかみさん奮戦記』(講談社)という、力士の育成や相撲部屋の経営をテーマにした本を出版しました。また、当時の中村部屋は、中卒で入門した力士に通信教育で高卒認定資格を取得させるなど、独自の育成方針で知られていたのです。その取り組みに興味を持ち、インタビューをさせてもらいました。
——その経験が、本書執筆の直接のきっかけになったのでしょうか?
山村 それに加えて、2015年の九州場所で、元横綱・北の湖が亡くなったことも大きかったです。子どもの頃のヒーローだったため、その訃報には大きな衝撃を受けました。そのとき、「相撲をきちんと分析したい」という思いが強まり、データを集めてみると、興味深い結果が次々と出てきたんです。
執筆のきっかけはイタリアでの在外研究
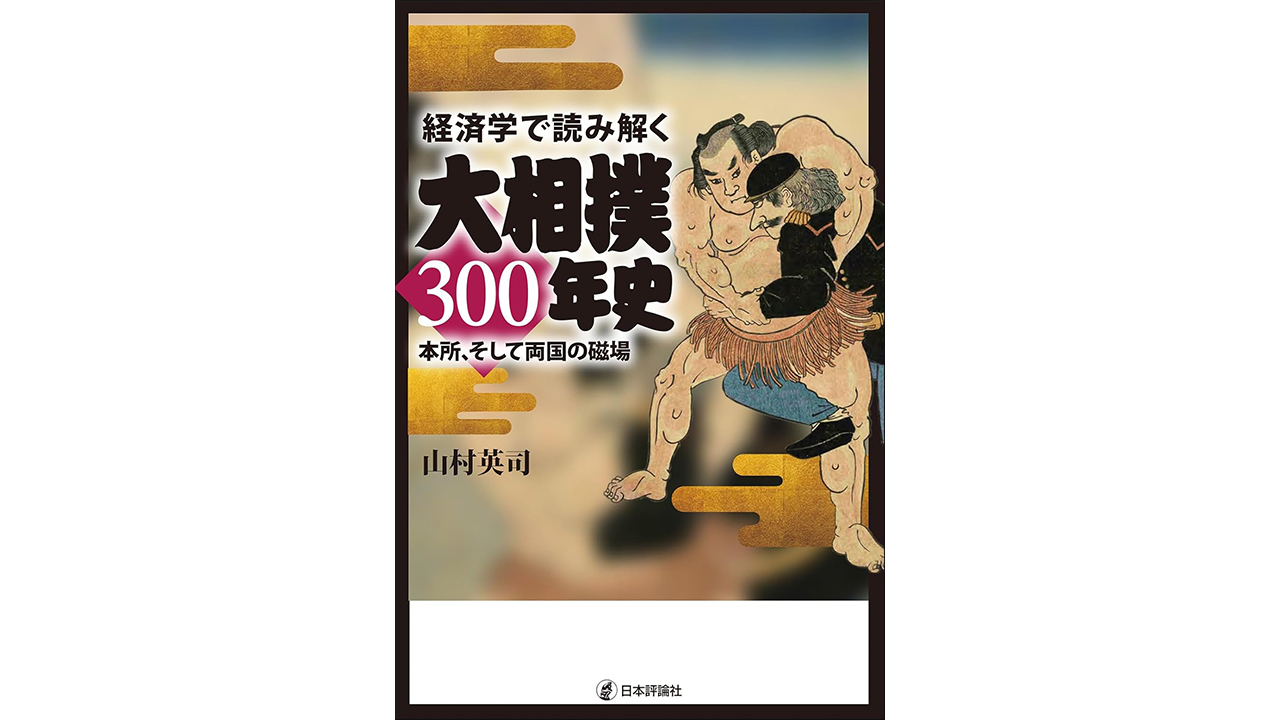
――山村さんの専門は経済学と心理学が融合した行動経済学です。これまで『義理と人情の経済学』(東洋経済新報社)など、さまざまなテーマで論文や本を執筆されてきました。
山村 相撲に関しても、当初は論文にしようと考えました。しかし、忙しさのあまり一時保留にします。そして、2023~24年に在外研究でイタリアに行ったのですが、そこでの経験が本を執筆する決定的な契機となりました。
—— イタリア!? 相撲とは距離がありそうですが……。
山村 そうですよね(笑)。でも、1年間じっくり時間が取れる環境だったので、ようやく「まとまったものを書こう」と決めました。
――海外に1年もいると、その地に関するテーマに興味を持ちそうな気もします。
山村 もちろん、パスタの研究にも没頭しました。ただ、イタリアでオペラや遺跡に触れるうちに、「日本人なのだから、日本の文化を伝えたい」という気持ちが強くなったんです。さらに、現地の研究者と話していると、意外にも相撲に詳しい人が多い。日本を旅行したときに本場所を生観戦したイタリア人もいて、「こんな力士いるよね」と昼食中に語り合うこともありました。そうした出来事が積み重なり、「これは本にしよう」と決意したのです。
——これまでに類を見ない相撲、そして経済学の本ですが、どのような点が特徴的でしょうか?
山村 「300年間の相撲を経済学で読み解く」という点ですね。本書では江戸時代からのデータを用い、北海道出身力士、外国人力士、モンゴル勢の影響など、時代ごとのトピックを分析し、明治、大正、昭和、平成、令和と一貫したストーリーにまとめました。私はデータ分析が得意なので、それを活かしながら「相撲の歴史」と「経済学」の接点を探りました。
——実は相撲に関するデータというのは膨大にあることを、本書で知りました。具体的にはどのような分析をされたのでしょうか?
山村 北海道出身力士の強さの背景や、外国人力士が横綱になれないのは本当に「差別」なのかといった議論ですね。データを基に分析すると、こうした主張が単純なものではないことが見えてきます。詳しい内容は、ぜひ本書で楽しんでいただければと思います(笑)。
——300年分のデータを用いるうえで意識したことはありますか?
山村 データが面白いだけでなく、その背景や文化をしっかりと描くことを重視しました。経済学では、データから仮説を検証する手法が一般的ですが、本書では「まず時代背景を描き、それを支えるデータ分析を行う」という構成にしました。
専門的だけどわかりやすい経済学の本
——本書の構成で意識した点はなんですか?
山村 全体の流れが分かるようにすることですね。経済学の本では、個々のトピックが独立していて、つながりが見えにくいものが多いのですが、本書ではすべての要素をひとつの流れの中に配置し、読者が自然に理解できる構成にしました。
――確かに。時代に沿って流れるように紹介されているため、「これどのページのデータだ?」と迷うことはありません。
山村 具体的には、グラフから始め、相関関係やデータを示しながら、前の話とどうつながるのかを明確にすることで、どこからでも振り返りやすいように工夫しました。そのため、読者が「前の章で出てきた話と、ここがつながるのか!」と直感的に理解できるような構成にしています。そこは特に強く意識しましたね。
——ほかの経済学の本とはどう違うのでしょうか?
山村 普通の経済学の本は仮説を立て、それを検証するためにデータを集めるという流れが一般的です。しかし、私はまず「相撲」という材料があって、それを描き出すための手段として経済学を使ったのです。
――さまざまな経済学の理論やアプローチが出てくるため、「こんなに研究方法があるのか」と思わされました。
山村 それと、経済学の本の中には、個々のトピックがバラバラでつながりが分かりにくいものも多いですが、本書では一貫したストーリーを持たせることを意識しました。データ分析はあくまでそのフレーム(枠組み)を作るためのものであり、読者が理解しやすいように丁寧に構成しています。
——それでは、執筆で苦労した点は?
山村 データの膨大な量を整理し、分かりやすいストーリーにまとめることですね。 細かい分析は論文向けですが、本書は一般向けの書籍なので、楽しめるようにポイントを押さえながら構成しました。
——専門知識のない一般読者に向けて意識したことはありますか?
山村 経済学が分からなくても読めるように、コラムを挿入し、文化や歴史の要素もふんだんに盛り込みました。Netflixのドラマ『サンクチュアリ-聖域』のイメージもあり、相撲は男性社会と思われがちですが、最近は「スー女(相撲好きの女性)」も増えているため、女性にも楽しんでもらえる内容に仕上げています。
——経済学はほとんど知らないのですが、驚くほどスラスラ読めました。ちなみに、本書はどんな人に読んでほしいですか?
山村 相撲ファンはもちろん、経済学や歴史に興味がある人にもぜひ読んでほしいですね。江戸の文化や街歩きが好きな人、現代と歴史のつながりに興味がある人にも楽しめる内容になっています。本書の刊行直前の2024年の九州場所中に、道産子横綱だった北の富士勝昭さんが亡くなりました。9年前の北の湖親方のように、同郷のヒーローが居住地の福岡で……(涙ぐむ)。「少しでも、あなたのような男に近づけるよう精進します」と天国の北の富士に伝えたいです。
――相撲を軸にした江戸時代の歴史はこれまで知らなかったため、驚きの連続でした。
山村 あと、個人的には、中村嗣子さんにもぜひ読んでもらいたいのですが、連絡先が分からず……。相撲協会にも問い合わせたのですが、不明とのことでした。もし、ご本人がこの記事を読んでいたら、ご連絡いただけるとうれしいです! 女将(おかみ)さん、あなたのお陰で書き上げることが出来ました。ありがとう!
(文=ゼロ次郎)
(取材・編集=サイゾーオンライン編集部)
山村英司(やまむら・えいじ)
1968年、北海道生まれ。西南学院大学経済学部教授。専門は行動経済学、経済発展論。著書に『義理と人情の経済学』(東洋経済新報社)、共著に『行動経済学の現在と未来』と『次世代の実証経済学』(共に日本評論社)がある。
