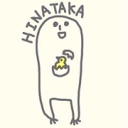【30日夜・地上波放送】土屋太鳳&福原遥『アイの歌声を聴かせて』劇中に隠された「ディズニー」「楳図かずお」オマージュとは?


2021年に劇場公開された際に熱狂的な口コミが寄せられ、第45回日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞を受賞した『アイの歌声を聴かせて』が、8月30日の20時45分よりNHK Eテレで地上波放送される。
本作の基本的なプロットは「ひとりぼっちの少女のところへ転校生のAI搭載ロボットがやってくる」とわかりやすく、子どもから大人まで分け隔てなく楽しめるので、ぜひゴールデンタイムに放送されるこの機会を逃さないでほしい。魅力を挙げると枚挙にいとまがないが、ここでは「朝ドラ俳優2人の声の演技」「ディズニーアニメおよび巨匠漫画家へのリスペクト」を中心に解説していこう。
※以下、『アイの歌声を聴かせて』の決定的なネタバレは避けたつもりですが、一部内容に触れています。
土屋太鳳がAIに共感を覚えたワケ「未熟さにコンプレックスを感じる」
『アイの歌声を聴かせて』は、2015年度前期の『まれ』の土屋太鳳、22年度後期の『舞いあがれ!』の福原遥という、共にNHK連続テレビ小説で主演を務めた国民的俳優2人による、実質的に「W主演」作品。しかも、2人は共に「自分とは似ていない」と感じた役を、これ以上は考えられないほど見事に演じている。
土屋が演じているのは女子高生AIの「シオン」で、「無機質なAI」と「純粋で可愛い女の子」という、本来であれば正反対の要素を同居させる演技を披露。劇中の最大の魅力といえる「ミュージカル」シーンでは「曲の個性に合わせて歌い方の個性も変える」挑戦もしており、特に「ジャズ柔道」のシーンでの「挑発的」にすら思える歌唱は必聴だ。
劇場パンフレットで土屋は自身が演じるシオンについて、「本当に女の子らしくて可愛いので、私にはあまり似ていない気がします」と謙遜しながらも、「周囲の人たちに幸せになってほしいと思いながら生きているところ」は似ているとも答えている。
さらに「女優としていろいろな経験をさせてもらっていますが、それぞれの分野のプロフェッショナルな方々と比べてしまうと、自分の未熟さにコンプレックスを感じるところもある」ことが、劇中のシオンの「どこか中途半端な場所にいる子」という印象と共通する、「機械とも人間とも言えない状況で揺れ動く彼女に共感してしまう」とも答えている。
確かに、シオンの「極端に明るいようで」「不安を抱えているような」「寄る辺のないような」印象を持たせる土屋の演技も、キャラクターに深みを与えていたのだ。
福原遥「相手に負けないように、内面の激しさが出るようにした」

福原遥が演じるのはひとりぼっちの少女「サトミ」。慈愛に満ちた振る舞いをしながらも、同時にとてつもない寂しさを抱えていることが繊細な声のトーンから伝わり、終盤では彼女が感情をはっきりと表に出すからこその感涙シーンも待ち受けている。
福原もまた「サトミはクールなタイプで、私と何から何まで違っています」と答えながらも、「ギャルっぽい女の子の『アヤ』に自分の意見を言うシーン」について「私の声質やスローなしゃべり方だと、相手に負けているように聞こえてしまう」ことを前提に、「力強く生きているサトミを表現するために、そういったシーンでは内面の激しさが出るように気を付けました」とも語っている。
まさにその通りで、表面的にはおとなしいタイプにも見える彼女が、「実はとても強い信念を持つ」ことも伝わってくることだろう。
ディズニー『ノートルダムの鐘』の悪役にそっくりなキャラも
『アイの歌声を聴かせて』の吉浦康裕監督は、1996年公開のディズニーアニメ映画『ノートルダムの鐘』と、82年から86年まで「ビッグコミックスピリッツ」(小学館)で連載された楳図かずおの長編SF漫画『わたしは真悟』へのリスペクトを明言している
アニメカルチャーメディア「Febri」のインタビュー記事では、吉浦監督は『ノートルダムの鐘』が「いつか日本アニメのスタイルで、こういったミュージカルアニメを作りたい」と思ったきっかけであることを語っている。
劇中にも明確なオマージュがあり、2013年公開の吉浦監督のアニメ映画『サカサマのパテマ』の「イザムラ」と、『アイの歌声を聴かせて』の「西城」は、見た目も性格も『ノートルダムの鐘』の「フロロー」という悪役にかなり似ている。
さらに、『アイの歌声を聴かせて』で土屋太鳳が歌唱する劇中歌「Umbrella」は、『ノートルダムの鐘』の「エスメラルダ」が聖堂で歌っているシーンが最初のイメージとしてあったそうで、カメラアングルがかなり似ているカットもある。
また、劇中のツインタワー「星間ビル」が実在する「ノートルダム大聖堂」の見た目にかなり近く、そのリスペクトはXで吉浦監督が火災前のノートルダム大聖堂に「聖地巡礼」している様子からもわかる。
裏テーマは『わたしは真悟』の「その後」だった
『わたしは真悟』へのリスペクトがはっきりとわかるのは、『アイの歌声を聴かせて』の「天野悟美(サトミ)」と「素崎十真(トウマ)」というキャラクターの名前を1文字ずつ取って並べると「真悟」なることだ。『わたしは真悟』の劇中のロボットも、自分の「両親」である少年「近藤悟(さとる)」と少女「山本真鈴(まりん)」の名前から1文字ずつ取って「真悟」と名付けている。
また、『わたしは真悟』のさとるとまりんが危険を冒して東京タワーの頂上を目指す様が、『アイの歌声を聴かせて』で主要キャラクターが一致団結して星間ビルに潜入する流れと、その頂上で重大な選択をする様と似ており(あるいは違っていて)、それは「人間の意識」という哲学的な思索を促す同作への、1つの「アンサー」とさえいえるものだった。
さらに、25年に開催された『新潟国際アニメーション映画祭』で、吉浦監督は「裏テーマとして、佐渡に行く直前で終わった楳図かずお先生の『私は真悟』のその後も描きたかった」とも明かしている。『アイの歌声を聴かせて』の舞台のモデルもまたはっきりと佐渡島であり、「AIが登場するジュブナイルSFもの」という枠組みにとどまらず、テーマとしても物語としても、『アイの歌声の聴かせて』は「ファンが作った『わたしは真悟』の最上級の二次創作であり続編」ともいえるのだ。
吉浦監督は24年に楳図かずおの訃報が伝えられた際に、Xで「楳図かずお先生の漫画を読んでいなければ『アイの歌声を聴かせて』も存在しなかったです」とも明言している。そのように先人へのリスペクトがふんだんにありながらも、圧倒的なオリジナリティーを備え、かつ万人が楽しめるエンターテインメントに仕上がっていることも称賛するしかない。
筆者個人は『アイの歌声を聴かせて』を50回以上観ているが、それでも観るたびに新しい発見がある、生涯オールタイムベスト、いや殿堂入りの歴史的大傑作だ。これから初めて見る方がうらやましくて仕方がない。ぜひとも地上波放送を“リアタイ”で楽しんでほしい。
(文=ヒナタカ)