『べらぼう』田沼意次はやはり黒幕か…そして失踪した唐丸はなぞの絵師「写楽」としていずれ再登場?
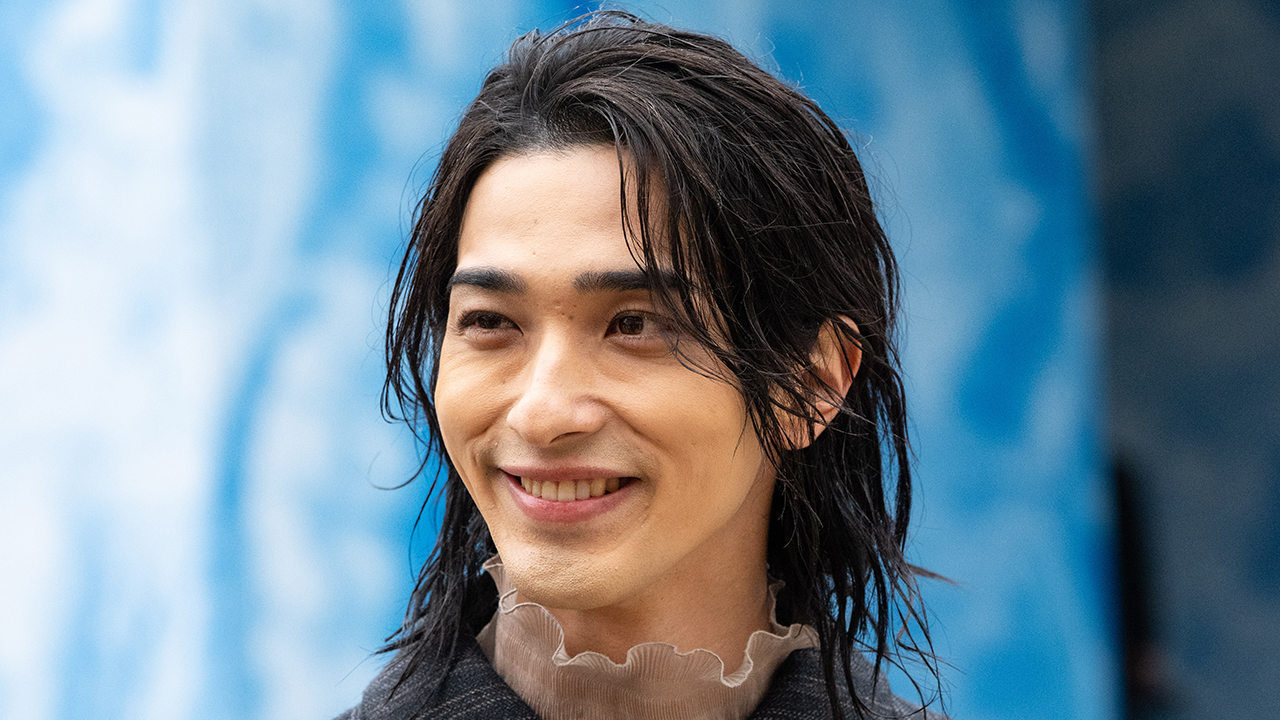
──歴史エッセイスト・堀江宏樹が国民的番組・大河ドラマ『べらぼう』に登場した人物や事象をテーマに、ドラマと史実の交差点を探るべく独自に考察。
先週(第5回)の『べらぼう』も楽しく拝見しました。
公式サイトによると、次回(第6回)のあらすじは、「蔦重(横浜流星)は、鱗形屋(片岡愛之助)と新たな青本を作る計画を始める。そんな中、須原屋(里見浩太朗)から『節用集』の偽板の話を聞き、蔦重にある疑念が生じる…」とのこと。
「節用集」とは「いろは引きの国語辞典」という意味です。鱗形屋で出版した「節用集」が関西の版元(板元)の「節用集」の丸パクリでトラブルになった事件が、物語の中心となっていきそうですね。
さて……前回のコラムでは、江戸時代になにか本を出すには、エンタメ本は「地本問屋」、学術書は「書物問屋」に所属しなきゃダメで~、みたいな話を、あくまでフワッとしていたと思います。
『べらぼう』は歴史ドラマですが、フィクションですから、どういう世界観なのかな?と思って様子見していたのですが、今週の放送で、里見浩太朗さんが演じる須原屋市兵衛が初登場。蔦重にお前さんが学術書を出したいのならともかく、エンタメ本を出したいのなら、そのために「株」を買うなんて必要はないんだよ(=お前さんは鱗形屋にダマされていたんだ)と、スパッと説明くださいました。
補足的にご説明しますと、江戸時代にはさまざまなビジネスごとに、「株仲間」といわれる同業者組合が結成されていました。「株」とは現代の語感とは異なり、営業権のイメージでとらえてください。
たとえば炭を扱う炭屋も、炭屋の株仲間に所属しなくては、大っぴらに営業していくことはできません。ドラマにも秩父の鉱山事業に失敗した窮地の平賀源内先生(安田顕さん)が、もともとは鉄を精錬するために火を燃やし続けねばならず、そのために作らせていた炭を売りさばいて挽回しようと発案、炭屋の「株」を得ようとしたシーンが出てきましたよね(ちなみに源内先生が秩父の炭を売ることで、一時的にせよ、多少潤ったのは史実です。が、原価率が低く、次第に先生も熱意を失って、秩父との関係は終了してしまいました)。
株仲間には厳格な定員がありました。そのビジネスに新規参入したいなら、もう辞めたいと思っている人から「株」を買わせてもらって、株仲間に入らせてもらわなくてはなりません。だから、源内先生は「株」を少しでも安く買おうとして、もう引退したい、廃業したいという炭屋の老旦那と交渉しまくっていたのですね。
ところが、学術本を扱う「書物問屋」は「株仲間」の制度を取り入れているのですが、エンタメ本を出している「地本問屋」には(少なくともこの時代)、そういう「株仲間」の制度が取り入れられておらず、ほかの同業者とうまくやるだけで、お仲間に加えてもらえたわけですね。
だから、ドラマの蔦重は大先輩にあたる鱗形屋の孫兵衛のもとであえて働くことで、暖簾分けしてもらえることを目指すというお話になったのでしょう。ただ、前回のコラムでも触れたとおり、ドラマでも描かれたようなトラブルが実はあったのかもしれませんが、基本的に史実の蔦重と鱗形屋孫兵衛の関係は親密でした。少なくとも次回のドラマで描かれるであろう、「『節用集』の偽板の話」が出てくるまでは仲が良かったようですよ(「節用集」を巡るトラブルについては前回お話しましたので、そちらをご覧ください)。おそらく来週の一回で、蔦屋が鱗形屋から独立するお話になっていきそうな気もしますね……。
唐丸は蔦重のところに戻ってくるのか?
さて、次回の放送内容ではテキストでは記させれていませんでしたが、次回の予告映像には、弓の稽古中の若君と、それをさも愛しそうに見守る高貴な身分の女性が映っていました。若君は、第10代将軍・徳川家治(眞島秀和さん)の嫡男の家基(幼名・竹千代、奥智哉さん)で、あの女性は家基の生母にして、家治の側室・お知保の方(高梨臨さん)だと思われます(ドラマでは「知保の方」)。
家治はある時期まで、本当に御台所(正室)・五十宮倫子だけにぞっこんでしたが、彼女との間には将軍継承権がない娘しか授かれず、それでお知保の方を「仕方なく」側室にした……という、女好きが多かった歴代将軍の中では異例の生真面目な人物でした。
そしてお知保との間に竹千代を授かり、その子が元気にすくすく成長してくれたわけですね。当時、将軍御台所が存命であれば、五十宮倫子が竹千代の母代わりとなって、つまりお知保の手から息子を奪って、自分の手元で養育することが普通でした。お知保も自分のお腹を痛めて産んだ息子を、倫子に取られてしまっていたのですが、彼女にとっては幸運なことに(?)、明和8年(1771年)に五十宮倫子が早逝したので、お知保も大々的に「御部屋様」として大奥の尊敬を集め、ああやってわが子とも気兼ねなく接することができていたという描かれ方なのでしょう。
しかし彼女の幸福の絶頂期は短く、安永8年(1779年)、それまで元気に鷹狩をしていた18歳の家基がとつぜん急病に倒れ、そのまま亡くなってしまったのです。田沼意次(渡辺謙さん)がこの事件の「黒幕」だったと創作物ではされがちですが、『べらぼう』ではどのように描くつもりでしょうか。『べらぼう』では、吉宗の文書を捏造させる「ワル」して描かれている田沼ですから、今後の暗躍が楽しみです……。
最後に前回(第5回)、「蔦に唐丸因果の蔓」の内容に戻ってみましょう。毎回、タイトルが粋という声が筆者の周辺にも多いのですが、今回はとくに良かったですね。ドラマの唐丸といえば、渡邉斗翔さんが名子役ぶりを見せつけてくれる存在でしたが、これで渡邉さんの出演は終わりでしょうか。
唐丸はドラマ第1回に吉原を襲った火事の最中に記憶喪失の少年として登場し、蔦重に助けられたのを縁として、行動を共にしていましたが、第5回(前回)では彼の正体を知っているらしい不審なお侍から強請(ゆす)られ、蔦屋のカネを銭箱ごと持ち出し、侍とともに入水して行方不明になってしまいました。
水に濡れて線がぼやけた下絵も即座に描き直してしまえる抜群の画才を発揮していたので、この子が『べらぼう』の喜多川歌麿? と思い始めていた筆者ですが、史実の蔦重から見た歌麿は、3歳年下なだけですし、失踪した唐丸を探す蔦重が10歳くらいのガキと言っていたので、さすがに唐丸=歌麿ではないな、と。
どうやら唐丸が成長して、「謎の絵師」東洲斎写楽となるのでしょうね。たしかに蔦重は写楽を「正体不明の謎の絵師」として、喜多川歌麿との関係がこじれている最中に彼のことを売り出しました。ただ現在、東洲斎写楽といえば、八丁堀あたりで暮らしていた阿波徳島藩主・蜂須賀家お抱えの能役者の斎藤十郎兵衛(生没年不詳)と書いている幕末の『増補浮世絵類考』という史料がありまして、写楽=斎藤十郎兵衛説が「ほぼ」定説として扱われることが多い気がします。
唐丸が斎藤十郎兵衛として蔦重のところに戻って来るのか、あるいはまったく別人として戻ってくるのか……この辺を『べらぼう』がどのように料理してくれるのか楽しみですね!
(文=堀江宏樹)
