『べらぼう』江戸時代の“大ベストセラー”かつ“タブー”だった「田沼騒動物」はどう生まれたのか?
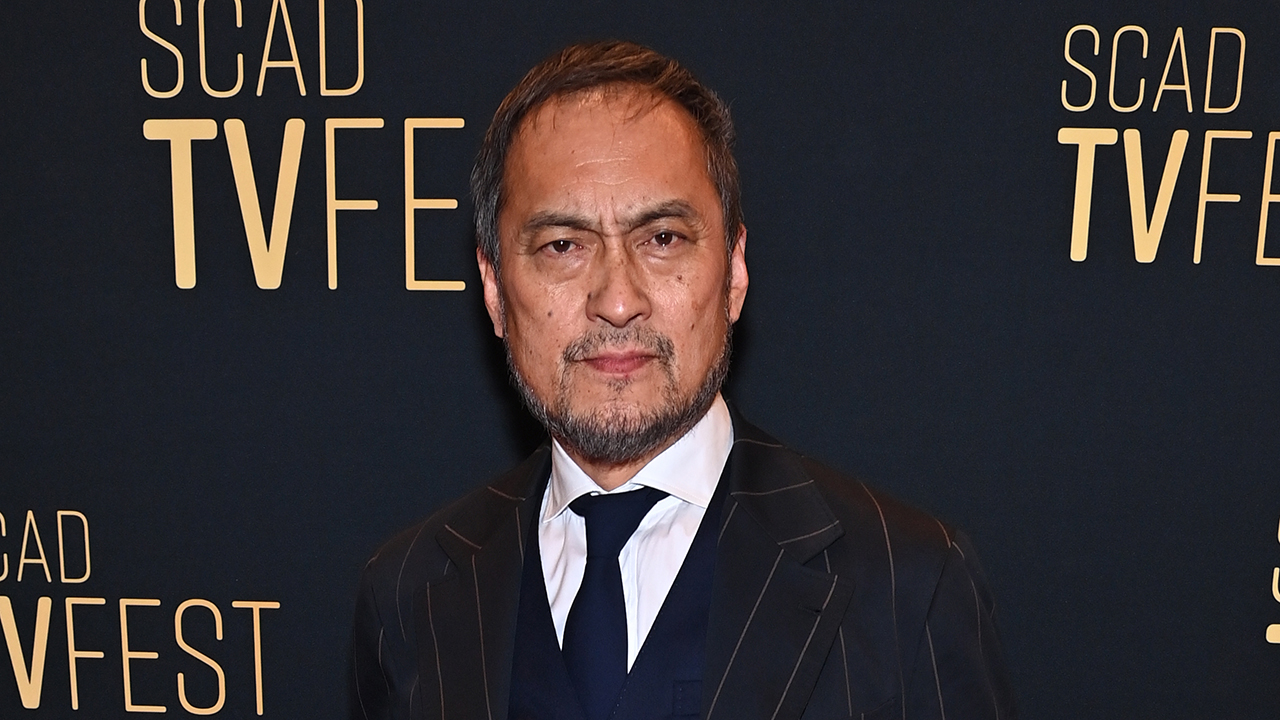
前回(第28回)の『べらぼう』は、『営中刃傷記』に記録されている佐野政言(矢本悠馬さん)が田沼意知(宮沢氷魚さん)に斬りつける前に発したとされるセリフ「覚えがあろう」も登場し、たくみに史実とフィクションがミックスされた内容で唸らせられました。ドラマの意知は最後まで政言のことを責めようとせず、身請けしてやる予定だった誰袖花魁(福原遥さん)のことを父・意次(渡辺謙さん)に頼んで事切れるという善人の中の善人でした。
史実では誰袖花魁は田沼意知の片腕だった旗本・土山宗次郎(ドラマでは柳俊太郎さん)が身請けしたことになっているのですが、役高350石の土山が誰袖花魁の身請けに必要だった1200両もの大金を本当に支払えたのかについては確かに疑問というしかありません。ドラマにも描かれたように裏に誰かがおり、代理で身請けさせたと考えるのもある意味、自然なんですね。
しかし、意知という後ろ盾を失った誰袖が頼りにするしかない土山宗次郎も天明6年(1786年)、徳川家治(ドラマでは眞島秀和さん)の急逝と田沼意次失脚にともなって地位を失っています。ドラマの時間軸が天明4年(1784年)あたりですから、誰袖の人生が再暗転するのは早くも2年後。実に不幸が絶えない苦労な女なのです。
さらに天明7年(1787年)、土山は横領の罪で逃亡のち斬首されており、誰袖がどうなってしまったかは不明。土山が彼女のために一財産だけでも残してくれていたら、江戸の町で小料理屋でもやってほそぼそと暮らしたのではないでしょうか……。あるいは古巣の吉原・大文字屋に戻って遊女屋家業を手伝ったのかもしれません。いずれにせよ、吉原の名店の名妓としてもてはやされたような華やかな生活は二度と戻ってこなかったはずです。
前回印象的だったのが、意知の死後、田沼意次の屋敷を蔦重(横浜流星さん)が訪ね、「裏で糸を引いている者がいる」と語ったシーンです。田沼も一橋治済(生田斗真さん)の関与を確信し、江戸城の廊下で口先だけのお悔やみを言う治済に対して睨みを利かせていましたが、渡辺謙さん、さすがの演技でしたね。
ただ、この先の歴史を考えると、「仇討ち」をしようとした田沼が、彼の権力の源泉といえる徳川家治とともに、「黒幕」の一橋治済に返り討ちにされる展開になってしまうのでしょう。――とすると「仇討ち」は誰に引き継がれるのか? という話となり、興味深いところですね。今後のドラマがより楽しみになりました。
今回はドラマの最後に放送される「紀行」でも触れられた『有職鎌倉山』など、田沼意次・意知父子のやりたい放題と、彼らの没落を描いた「田沼騒動物」が明治時代になるまで人気を博したというお話から触れていきましょうか……。
松平定信という人物はどう描かれるのか?
江戸時代の庶民が大好きだったジャンルが、この手の「お家騒動物」なんですね。しかし、江戸幕府は将軍や幕府の政治家たちを創作物に登場させることを固く禁じていました。
それではなぜ「田沼騒動物」の出版が可能だったかというと、時代を平安、鎌倉時代など過去に移して、登場人物の名前も適宜変更し、それとなく当時の批判したい政治状況に似せた作品背景を作り出すことで「これはフィクションです」「実在の人物や団体とは関係ありません」という言い訳をするわけです。
たとえば「田沼騒動物」の大ベストセラーで、寛政元年(1789年)刊行の『天下一面鏡梅鉢(てんかいちめんかがみのうめばち)』という作品(全3冊)では、醍醐天皇と菅原道真が生きていた平安時代に時代背景を移し、当時の政治状況を風刺する内容にしています。
しかし先述のように、将軍や幕府の政治家たちを創作物に登場させるのはご法度でしたから、この作品は(一説に)蔦屋重三郎率いる蔦屋耕書堂から発売されたにもかかわらず、冊子のどこにも蔦屋の名前は見られないのです。これも幕府の取り締まりを逃れるためですね。
のちには綱紀粛正と徹底的倹約主義で知られる「寛政の改革」を主導したことで、ひたすらに生真面目な印象が強い松平定信(ドラマでは井上祐貴さん)ですが、こうした田沼時代を批判した傾向が強い黄表紙については年単位で長い黙認を続けていました。
松平定信としては、将軍が11代将軍・徳川家斉(ドラマでは城桧吏さん)に代替わりしたというタイミングもあり、前将軍・家治の治世=「田沼時代」を、賄賂や汚職が横行した嘆かわしい時代として葬り去ろうとしていたのでしょう。そのためには本来ならご法度の政権批判をふくむ黄表紙などもわざと泳がせ、放置していたのだと推測されます。
実は松平定信も田沼同様、清濁併せ持つタイプでした。かつては定信も田沼に賄賂を送っているんですよ。徳川宗家に跡継ぎがいない場合、将軍を輩出できる御三卿のひとつ、田安家に生まれたことが誇りの定信は、理由あって白河藩(現在の福島県白河市)の藩主の養子となり、その座を継ぎました。白河藩主としては財政立て直しに尽力し、有名になりましたが、地方の一藩主として終わるつもりなどさらさらなかったのです。
当時、江戸城内では登城時の詰所が「どの部屋か」で、大名家のステイタスが視覚化されていました。白河藩主・松平家は臣下の大名にとっては最高の詰所・「溜之間」に入ることが許されておらず、そこに座れるようになることが悲願だったのです。溜之間詰めの大名となると政治的発言力が上がるという側面もありました。
それゆえ定信は田沼意次の屋敷まで日参し、「銀の花活け」や「数百両」などのお土産を渡し、ようやく「定信一代限り」という条件付きで溜之間詰めの大名というステイタスを入手成功したのでした(高澤憲治『松平定信』)。
つまり金権政治のうま味も存分に知っている松平定信が、田沼意次を汚職政治家として切り捨てたことは、騙されやすい江戸っ子に対するポーズでしかなかった……ということなのですね。
それでも松平定信という人物については、謹厳実直な部分も目立つ気はします。『源氏物語』全文を生涯で何度も書写したことは有名です。さらに彼が28歳のときに書いた、その名も『修行録』という随筆では、定信に惚れていた娘の結婚が決まり、明日、田舎に帰ってしまうという前夜、娘と定信が同じ布団で過ごすシーンが出てきます。
それのどこが謹厳実直と思うかもしれませんが、定信は娘に添い寝し、結婚する女の心得を延々と説いて聞かせ続けたのでした。つまり、最後にお説教――娘が哀れでなりません。
それについて本人は「いささか凡情はおこらず」と感想を書いていますが、凡人のようにムラムラッとしなかった自分を聖人君子アピールできると考えていたようです。定信はその娘に昔、手をつけていたが、性格がイヤで遠ざけたかったのになかなか結婚しなかったので困っていたところ、やっと縁組が決まったので、送り出す前の晩のこと「だけ」書いたという説もありますが……まとめるとただのクズ男になっちゃいますね。
こういう定信ですから、精力過多のオットセイ将軍と一部で有名で、55人かそれ以上の子沢山だった家斉将軍にも公然と「やりすぎィ(超訳)」と突っ込みしたり、あまりに空気を読めないところから失脚させられたという話もあります。
世間の考える「普通」と少し、しかし確実にズレているところが、松平定信の最大の強みであり、弱点でもあったのではないでしょうか。ドラマでもそろそろ再登場してくる頃かと思いますが、定信という男がどのように描かれていくのか楽しみです。
(文=堀江宏樹)
