『べらぼう』「犬を食え」発言の真相、そして新之助による“打ちこわし≒喧嘩”は本当に暴動ではなかったのか?
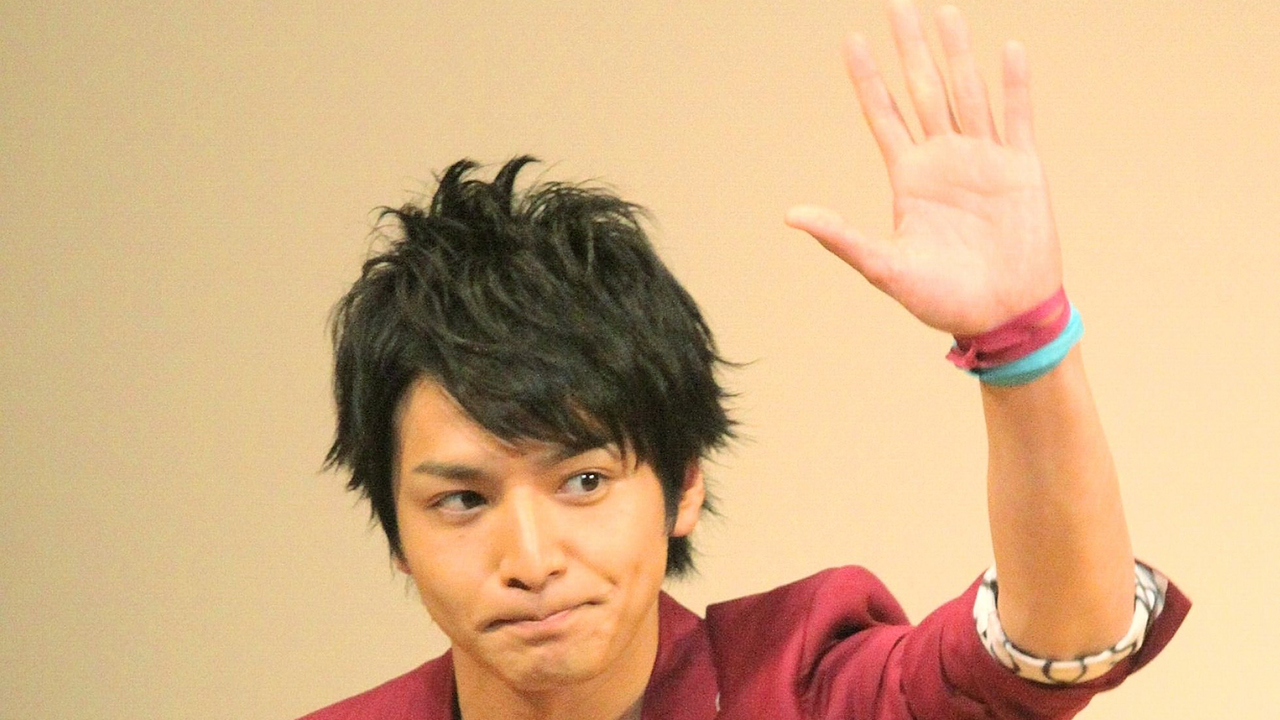
前回(第32回)の『べらぼう』の中でもっともネットを騒がせたのは、物乞いの扮装で市中にくりだした一橋治済(生田斗真さん)の姿だったように思います。
いつもなら屋敷で采配するだけで、実務は手下の男にすべて任せていましたが、今回は手下こと“丈右衛門だった男(矢野聖人さん)”と「お役人さまから米がなければ犬を捕まえて食えと言われました……」「なんと! 犬を食えなどと言われたのかー!」とコンビで熱演していましたね。
「将軍の父親」という肩書以外にまともな(政治)経験がないと指摘されたのが気に障ったのでしょうか、思わず笑ってしまった筆者ですが、史実を上手に取り込んでくるなぁと感心もしていました。
最初に、ドラマの現在の時間軸は、天明7年(1787年)であることを確認しておきますね。
江戸町奉行の曲淵景漸(まがりぶち・かげつぐ)なる人物――あの佐野政言(矢本悠馬さん)に切腹の判決を下した男でもあるのですが、その曲淵が天明7年5月、「米がないし、お役人は諸国からかき集めた米がもうすぐ江戸に到着する、などというが、もうわれわれは待てない!」といって一歩も引かない町年寄(=町人の代表者)に対し、「むかし飢饉のときは犬を食ったものだ」などと言い放ったせいで、打ちこわしが起きた(水野為長『よしの冊子』)という逸話があるのです。
松平定信(井上祐貴さん)の側近である水野が『よしの冊子』を執筆したのは、江戸城の政治家としては経験不足のまま、政権の中枢に入ることになった松平定信からの要請があったからだと語られます。
本当に町奉行・曲淵景漸による「貧乏人は犬を食え」発言があったのかどうか、それが江戸市中における天明の打ちこわしの直接の原因だったかはともかく、5代将軍・徳川綱吉が「犬は食べたらダメ絶対!」と言い出すまでは(おそらく、その後も食糧不足の厳冬などは)市中の野良犬を捕まえ、食べる貧民の姿が散見されていたものなのですね。
また、一橋治済たちのやり取りを本気にした新之助(井之脇海さん)が「お上の考えしかと受け取った!」といって、打ちこわしを始めようとするのですが、ここに蔦重(横浜流星さん)が(血の気の多い長屋の若い衆にリンチされながらも)「主張をココに書いてくれ」と白い布を持ち込んだり、いろいろと絡んでいました。
要するに米を出し惜しみし、高値をつけたままの米問屋に攻め入って、奪い取るのであれば、当時の法からしても重罪の「暴動」の扱いなのですが、米問屋に自分の主義主張を書いて攻め込み、打ちこわしするのであれば、江戸の庶民vs米問屋の「喧嘩」という構図になるから、罪は問われても軽いはず……というあたり、面白かったですね。
史実でも江戸の打ちこわし騒動は当初、目撃者の旗本・森山孝盛の言葉によると、「誠に丁寧礼儀正しく狼藉」していたようなのです。いわく町人たちは、米問屋の店と家屋だけを打ちこわし、隣の家に被害が出ないように細心の注意を払った。勢いに乗じて盗みなどを働こうとした者を食い止めたなど、奇異に思えるようなルールに乗っ取って行動をしていたのです。
ただ、それも打ちこわしが発生しはじめた天明7年7月20日から数日間の話。その後は関東全域から政治に不平不満を抱いた暴徒たちがぞくぞくと「上京」し、22日ごろを境目として、暴れまわり、家屋を引き倒し、略奪行為も平然と行う姿が目立つようになったのでした。「江戸市中が打ちこわしで大混乱」との噂は諸国にも瞬く間に伝わり、「上総、房州より江戸の端々へ集まり来て家壊し狼藉をなす(吉田正直『尾農葉栗見聞集』)」と、美濃(現在の愛知県)の役人の手でも記されています。
いずれにせよ、全国各地で断続的に発生した打ちこわし騒動こそが、田沼政権の完全な終わりを意味していたのです。
松平定信はどう描かれていくのか?
田沼意次(渡辺謙さん)は商業政策を重視し、株仲間(商工組合)を保護したため、商業活動は活発化したのですが、同時に一部の大商人たちに市場を独占する力を与えてしまっていました。
飢饉が発生した際、これらの商人が米を買い占めたり売り惜しんだりした結果、米価は高騰し、庶民たちは米を入手できなくなり、不満が高まる中、「すべて田沼意次が悪い」という声が高まってしまったのです。
ちなみに松平定信にとっては、これらの不幸は、願ってもない幸運にほかなりませんでした。以前のコラムでも、松平定信は田沼意次に現金や「銀の花活け」などをせっせと贈って、その見返りとして「一代限り」と限定されながらも、溜之間詰めの大名に出世できた……という話をしてきました。溜之間の大名になるということは、政治的発言力を持つのと同義だったのです。
そんな松平の目前で、目の上のタンコブでしかなかった田沼意次は後ろ盾の10代将軍・徳川家治(眞島秀和さん)を亡くし、これを契機に没落していきます。
おまけに田沼の重商主義的政策の陰でのさばった商人の存在が原因となった米の価格高騰や、打ちこわし騒動が発生する中、「伝説のカリスマ」だった8代将軍・吉宗の孫という血筋を誇り、田沼時代には不遇をかこちつつも東北を襲った飢饉の中でも餓死者を出さなかった白河藩主・松平定信を「新しきカリスマ」として推す声が江戸城内に増えていったのですね。
前回のドラマでは田沼意次は老中職を失い、彼の側近たちの多くが失職したものの、隠然たる影響力は江戸城内に残しており、阿部正倫(須田邦裕さん)など田沼派の大名が新たに老中に登用されたという描写もありました。
ただ、これはあくまでドラマの話です。田沼派の老中・阿部正倫は実在しますが、田沼意次の失脚に連座しなくてよかったのは、彼が家康の時代から続く名門譜代大名の阿部家出身であることなどが理由だったのでしょう。
しかしさすがの阿部も、松平定信によって、老中就任の翌年――つまり早くも天明8年(1788年)には追い落とされてしまったのです。
当時の松平定信は、自身を「質素倹約を重んじ、清廉潔白な次世代のリーダー候補」としてアピールしまくりました。そして天明7年6月、30歳の若さで老中になった直後、老中たちのまとめ役である老中首座にも就任。さらに年少の11代将軍・徳川家斉(城桧吏さん)の後見人として、将軍補佐役となりました。
こうして名実ともに幕政の最高権力者となった松平定信の手で、「寛政の改革」が本格的に開始されていくのでした。このあたり、『べらぼう』では文字通りドラマティックに演出されていくと思われます。
また白河藩主としての松平家について、ドラマでは老中にするには「家柄がふさわしくない」とするセリフもありました。ただ、これについて筆者の周辺では「本当にそうだったの?」という声もあったので補足させていただきます。
松平定信が養子として入った白河藩主・松平家は、徳川家の分家筋では「久松松平家」と称されます。そして久松松平家は、徳川家康の生母・於大の方が、彼女の再婚相手である久松長家との間に成した子どもたちと、その子孫たちで構成されるれっきとした「名門」です。
久松長家といえば、『どうする家康』ではリリー・フランキーさんが演じた姿が思い出されるわけですが、徳川家康の異父兄弟である彼らの子孫なのだから、その後の江戸城でも「名門」として遇されることは間違いない。しかし、本当に強い政治的発言力を有する家康の子孫たち――たとえば将軍家や、御三家や御三卿などとは家格が劣る存在にすぎない……という事実上の区別はされていたのです。
幕府最上層の人々の間にも明確な区別が敷かれていた時代背景を巧みにドラマは描いているなぁ、と思って拝見していました。今後、ドラマの松平定信がどう描かれていくのか、本当に楽しみです。
(文=堀江宏樹)
