ノーベル文学賞作家ハン・ガンが描く韓国の負の歴史…「光州事件」「4・3事件」とカルチャーの関係
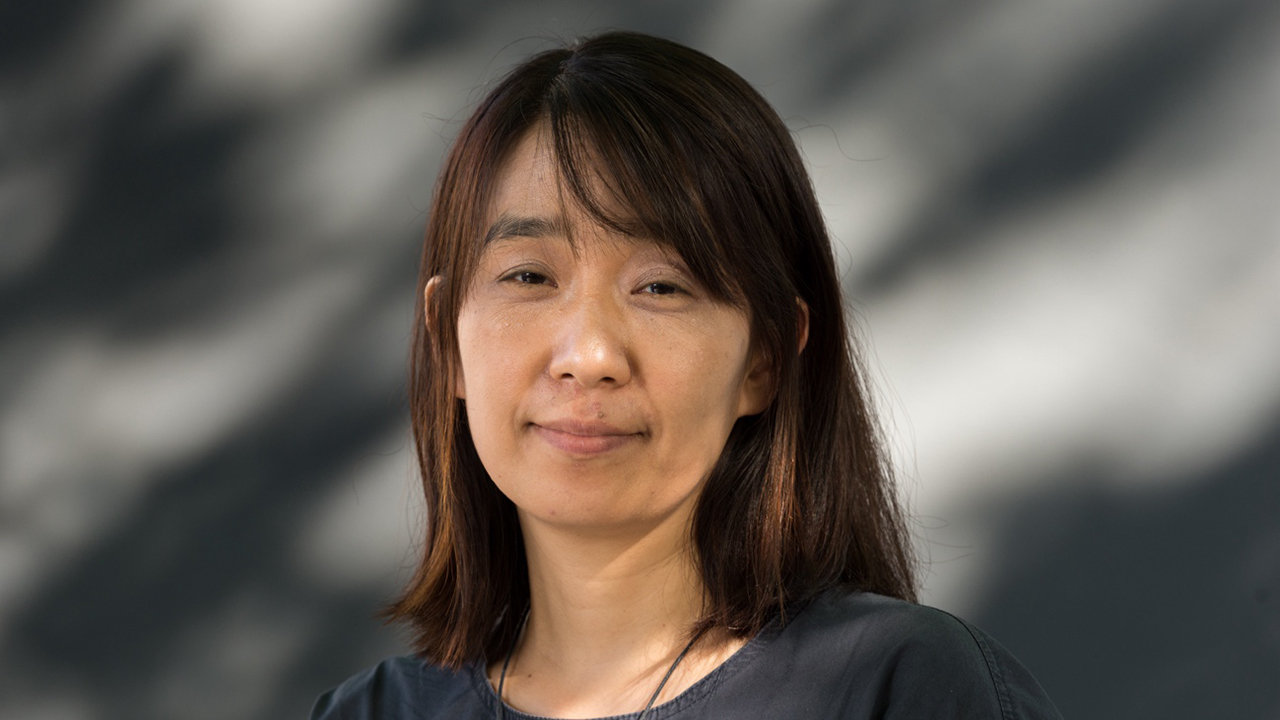
今年のノーベル文学賞を受賞した韓江(ハン・ガン)は、「光州事件」や「4・3事件」をテーマにした作品で、歴史の忘却に抵抗し、過去のトラウマに向き合う視点が特徴的だ。
近年、K-POPだけでなくK-文学やK-ムービーも注目を集める中、これらの歴史的事件が作品で描かれることが多いが、その背景や実態については日本で十分に知られていないのが現状だ。そこで、このような題材が韓国のポップカルチャーでたびたび描かれる理由について、文化人類学者の土佐昌樹教授に解説してもらった。
世界的に存在感を増してきた「韓国文学(K-文学)」
――アジアの女性として初めてノーベル文学賞を受賞した韓江(ハン・ガン)氏ですが、韓国人としては2000年に「南北首脳会議」を初めて実現させた功績を讃えられ、平和賞を受賞した金大中(キム・デジュン)元大統領以来、24年ぶりの受賞となります。分野は違いますが、今回の受賞についてどのような印象を受けられましたか?
土佐昌樹教授(以下、土佐) いろいろな意味で喜ばしい出来事には違いありません。しかし、文学というのは経済効果やわかりやすい成長指標とすぐ結びつく分野ではないため、韓国社会のはしゃぎぶりを見ていると、ゴールドラッシュでにわかに沸き立った一過性のブームを見ているような危うさも感じます。
――それはなぜでしょうか?
土佐 授賞理由に「過去のトラウマに立ち向かい、人間の命のもろさをあらわにする強烈な詩的散文」とあったように、韓江氏の小説には韓国社会の負の歴史や人間の弱さを見つめ直すテーマが多いです。たとえ、これを機に彼女の小説を初めて手にする人が韓国文化の優秀さを再確認したいと思ったとしても、その期待はすぐ裏切られることになり、ブーム自体は早晩過ぎ去るでしょう。
――BTS(防弾少年団)などK-POPグループが世界的な音楽賞を受賞したときと同じように、手放しでは喜べないということですね。
土佐 それでも、いろいろな意味で喜ばしいと述べたのは、主に2つの理由からです。第一に、そのような負の歴史を見つめ直す視線が一時でも社会の大きな注目を集めたこと。第二に、日本と同じく女性の地位が遅々として向上せず、それどころか近年は「女性嫌悪」の風潮が目立っている韓国で、女性の表現者にスポットライトが当たったこと。そういう意味で、この授賞は明らかにマイノリティに対するエンパワーメントの側面が強かったと思います。「日本原水爆被害者団体協議会」のノーベル平和賞受賞と同じく、すぐに金儲けに結びつく分野でなくても、人類の生存という大きな目的のためには、地道な実践や表現がどれほど重要なのか、改めて考えさせてくれるメッセージが込められていたと思います。
――2018年に『82年生まれ、キム・ジヨン』(筑摩書房)が日本でも29万部超えのベストセラーを記録して以降、同作のようなフェミニズム系の韓国文学が女性を中心に評判を呼んでいます。近年の「韓国文学(K-文学)ブーム」の人気をどのように考えますか?
土佐 まず、小説が代表する現代文学は、基本的にはすべて「世界文学」だと思います。アルベール・カミュやガブリエル・ガルシア=マルケスを読まずに小説を書いている作家は、世界のどこにもいないでしょう。そのような世界文学を吸収したうえで、日本の現代小説も書かれています。そして、今度は安部公房、大江健三郎、村上春樹といった作家の作品が翻訳され、海外でも読まれるようになっています。世界文学は閉じたものではなく、日々増殖を続けている生き物であり、「韓国文学」というものも、そうした動的ネットワークの一部として存在感を増しているということです。
その中でも、『82年生まれ、キム・ジヨン』のチョ・ナムジュや『走れ、オヤジ殿』(晶文社)のキム・エランなど、女性作家の活躍が非常に目立っています。文学にはそもそもそういう傾向がありますが、彼女らの視線は社会の弱い部分に向けられます。それが海外の読者の共感を呼んでいるわけです。
――韓江氏の作品も『すべての、白いものたちの』(河出書房新社)や『菜食主義者』(クオン)などが2010年代から翻訳されていたこともあり、ノーベル賞受賞前から日本でもその名は知られていました。
土佐 今のところ、韓国文学の海外での紹介は日本がもっとも進んでいると思います。それは、言語的文化的に近いという背景に加え、近代化に伴う同じような「正負の遺産」を共有しているからです。日本は少なくとも戦後は軍事政権にはならなかったわけですが、それでも経済成長優先で国民を動員し、効率のいい社会を作ってきた点はまったく同じでした。その成果として高い経済成長がありましたが、その裏には当然大きな副作用がありました。ストレスに満ちた競争社会を作った結果、高い自殺率、低い幸福度、いじめ問題、「ひきこもり」の蔓延など、両国が抱える社会的矛盾や社会病理の兆候は、驚くほど似ています。女性の社会的地位の低さも共通しており、だからこそ『82年生まれ、キム・ジヨン』は日本の女性に我がことのように受け入れられたわけです。
社会の弱さに向けられた女性作家の作品が、日本だけでなく新自由主義が進行するグローバルな規模で共感の輪を広げているとしたら、単純に歓迎すべき事態ではないでしょう。しかし、残念ながら世界は今そういう方向に向かっているのだと思います。
――なんだか、せっかくのブームなのにその背景を知るとモヤモヤしてしまいますね。
土佐 それと、日本で韓国文学のファンが多いのは、安宇植(アン・ウシク)や斎藤真理子など優れた翻訳者が地道に翻訳紹介してきた貢献も大きいと思います。私も文化人類学者として文化の翻訳を生業にしているため、なおさら痛感するのですが、たとえ韓国語は日本語と近いといってもやはり外国語なので、小説の緻密な表現を翻訳するという作業の難しさは、並大抵のことではありません。翻訳とは、言葉を単純に移し替える作業でなく、創造的に異文化理解の架け橋をすることだからです。韓江の小説の多くはデボラ・スミスというイギリス人女性が英訳したそうですが、ノーベル賞の対象になったのは、そうした翻訳者の貢献が非常に大きいと思います。
韓国の負の歴史「光州事件」と「4・3事件」とは?
――かつての韓国は朴正煕(パク・チョンヒ)元大統領から全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領両政権の26年間にわたり軍事独裁国家でした。そして、「光州事件」は朴正煕元大統領の暗殺後に発生しています。
1980年5月18日、全斗煥将軍(当時)による軍事クーデターに抗議した学生・市民の大衆運動が、戒厳令を布いた韓国軍によって軍事鎮圧され、多数の死傷者を出します。しかし、その後、大統領となる全斗煥将軍は、この事件に関する情報のすべてを統制・隠蔽しました。光州事件が後の韓国社会に与えた影響は、どれほどのものだったのでしょうか?
土佐 それは簡単に測れるものではありません。戦後の日本ではなかなか想像できないと思いますが、自国民を守るはずの軍隊が市民に銃口を向け、大量の死傷者を出しても撃ち続けるということが、どのような論理と感情で可能となったのか……。とてつもなく重い問題ですが、同時に極めて単純な問題でもあります。要は、銃口を向けた相手を「敵」と思い込めばいいのですから。それは、あるときは「アカ(共産主義者)」、あるときは「暴徒」と定義づけられました。
しかし、本当の問題はそれからです。そのような悲惨な出来事を経たあとに、加害者と被害者が「同じ国民」として、どうしたらうまくやっていくことができるでしょうか? 和解や相互理解は可能でしょうか? そんなことは、端的に不可能です。そこには、永遠に解のない重い問いが立ちふさがるしかないのです。
――そのような背景もあってか、10月10日付「毎日新聞」の「ノーベル文学賞の韓江氏『美しさと暴力が共存する世界に苦痛感じる』」という記事では、彼女が韓国メディアのインタビューで「光州民主化運動が人生を変えた」と述べたことが紹介されました。
土佐 韓国がその後、民主化を実現した結果、暴徒の烙印を押された人々には名誉回復がなされ、犠牲者に対しては補償金が支給されました。政治的には一応決着し、光州は民主化運動の聖地と呼ばれるに至りました。しかし、それで本当に犠牲者の魂は救われるでしょうか? それはもはや政治の問題ではなく、宗教や文学しか扱えない魂の問題です。この問題にどう向き合うかは、韓国で表現者として生きていくにあたり、避けて通れないといったら言い過ぎかもしれませんが、それくらい重い十字架としてのしかかっていると思います。
――ところで、1988年に国民投票で大統領直接選挙制を軸とする憲法改正が実現し、盧泰愚(ノ・テウ)大統領が誕生した「第六共和国」政体になるまで、同国と日本の関係はどういうものだったのでしょうか?
土佐 韓国現代史には国家権力が引き起こしたいくつもの悲惨な出来事が起きていますが、その代表が1980年5月の光州事件と、1948年4月3日に始まった済州島民蜂起に対する虐殺、いわゆる「4・3事件」でした。後者は米軍政下に起きていますし、光州事件も米政府の黙認がなければ起きなかった可能性があります。日本の保守政権は、いずれに対しても黙認以上の介入をしようとはしませんでした。日韓いずれの政府も、人の命よりは経済的実利を重んじる姿勢であり、また大きな対価を払おうとも反共戦線を維持するための国家統合を優先していた時代でした。
一方で、韓国の反体制知識人と日本の知識人が支え合う面もありました。しかし、大江健三郎が韓国を代表する抵抗詩人、金芝河(キム・ジハ)に連帯を呼びかけたところ、逆に植民地支配の加害者としての責任を追及されたという苦い出来事もありました。政府同士の関係には欺瞞的な馴れ合いがあったと言えるかもしれませんが、かといって市民同士の関係もすぐ腹を割って対等にというわけにもいかなかった時代です。
――光州事件は前出の映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』やBTSの「Ma City」という楽曲など、40年以上経った今でもポップカルチャーで題材になっています。韓江氏同様、なぜこの事件に影響を受けたクリエイターや作品は多いのでしょうか?
土佐 先ほども触れましたが、韓国現代史にとってこの出来事が一種の十字架の意味を持つからです。韓国の民主化は、あのときの光州市民の犠牲の上に成り立っており、それを忘れることなく表現し続けることが、犠牲者に対してできる唯一の鎮魂だということかもしれません。
韓国の現代史には、軍事政権下で表現を許されなかった出来事がたくさんあり、とりわけ民主化以降の韓国映画は、そうしたタブーを競うように作品化して上映しました。ベトナム戦争への派兵を描いた『ホワイト・バッジ』が1992年に上映されましたが、本作はタブーへの挑戦を告げる最初の作品だったのではないかと思います。ヒット作になりましたが、退役軍人団体から非難されました。その後に続く流れまで数年待つ必要がありましたが、事前検閲制度が1996年に廃止されたことが大きいと思います。
文学もまた、軍事政権下では表現の制限を課せらされていましたが、それでも政権批判を含め、まだ放任されているほうでした。金芝河は何度も逮捕されながら、詩の出版をやめませんでした。彼は特別な例ですが、一般に文学の出版の規模は限られています。それに比べ、音楽、映画、テレビ番組といったより大衆的なメディアは、もっと厳しい検閲にさらされました。結果、国内文化産業は抑圧され、禁じられているはずの日本文化の海賊版が横行するというありさまで、あのままだったら韓国のドラマやポップスが海外に進出するような成長を遂げることはなかったでしょう。
――K-POPから入った若い世代は知る由もありませんが、1998年に金大中大統領が受け入れを認めるまで、韓国内で日本の大衆文化は禁止・規制されていました。そこから、どのようにして同国は今のカルチャーシーンの第一線で活躍するクリエイターたちを生み出せたのでしょうか?
土佐 同国の文化産業が躍進するもうひとつのきっかけが、1997年のIMF危機です。タイから始まったアジアの通貨危機は韓国に及び、国内の金融制度が破綻し、多くの企業が倒産するか大規模なリストラを敢行するかを迫られました。結果、多くの若い失業者があふれましたが、一方で新しい才能と資本が文化セクターに流れ込むきっかけともなりました。よく言われるように、最大の危機は最大のチャンスだったわけです。当事者にとっては、そんな楽観的なものではなかったはずで、これをきっかけに韓国企業はますます厳しい生き残り戦略を身につけ、過酷な競争社会を実現することになりました。ただ、崖っぷちの境地を突きつけられた才能が、この時期に大胆な創造の試みを繰り返すことがなければ、K-POPや韓国映画の華々しい世界進出は起こらなかったと思います。
済州島と全羅道に対する地域差別とは?
――そこから、どのようにして負の歴史が小説化や映画化につながるのでしょうか?
土佐 民主化とIMF危機という2つの条件を重ね合わせてみると、韓国現代史でタブーであった題材を好んで映画化することと、大衆的ヒット作を作り出すことは、必ずしも矛盾しなかった理由がわかります。日本で初めて観客動員100万人を実現し、韓国映画に対する広い関心を呼び起こした『シュリ』(1999年)は、ハリウッド並みのブロックバスターという触れ込みでしたが、同時にそれは南北分断の厳しい現実を正面から描いている作品でもあります。その後、金日成暗殺を狙った秘密部隊の存在を暴いた『シルミド』(2003年)、朝鮮戦争の悲劇を反省的に描いた『ブラザーフッド』(2004年)、光州事件を描いた『光州5・18』(2007年)などの大作が作られ、いずれも大ヒットを記録しています。韓国映画の活況の一因は、国際映画祭で受賞するようなアート系や社会派の作品と、いわゆる娯楽大作が分離しておらず、うまく統合されていることにあると思います。今挙げたいずれの作品も、韓国現代史の重いタブーを扱いながら、それが同時に大衆娯楽としても楽しめる高いクオリティの作品になっています。社会派と娯楽化の結合という傾向は、アカデミー賞作品賞を受賞したポン・ジュノ監督の『パラサイト 半地下の家族』(2019年)や、全斗煥による軍事クーデターを描いた『ソウルの春』(2023年)に至るまで続いています。
――日本でも人気を集めた「韓流映画」のほとんどは、同国の社会問題や歴史問題を取り扱ったものが多い気がします。
土佐 そのこととも関係ありますが、韓国映画には重いテーマを扱った小説を映画化した例がかなり多いといえるでしょう。韓江の小説も、『菜食主義者』(2009年)と『傷跡』(2011年)が映画化されています。また、小説家イ・チャンドンは、IMF危機の起きた1997年に映画監督に転身し、2作目の作品が『ペパーミント・キャンディー』(2000年)でした。民主化運動に積極的に関わっていた彼はその後、文化観光部長官にも就任しています。
小説と映画をつなぐそうした表現の世界で、とりわけ民主化以降の韓国において、光州事件はやはり特別な位置づけにあります。映画『ペパーミント・キャンディー』は、若い兵士として動員されたひとりの男が、誤って少女を撃ち殺してしまう出来事から人生を狂わせていくプロセスを、時間を逆行する手法で描いています。映画『光州5・18』や小説『少年が来る』(クオン)は、被害者の側から光州事件を描いています。どちらも登場人物の人生が破滅するわけで、被害者と加害者という単純な図式で割り切れない悲劇の複雑さが描かれています。
――在日朝鮮人の作家・金石範氏が1976〜97年にかけて発表した『火山島』(全7巻/文藝春秋)は4・3事件が題材となっています。この事件も韓国現代史最大のタブーとされていますが、ここで気になるのが同国における済州島と光州事件の起きた全羅道への地域差別です。今でも根強く残っていると言われていますが、これはどういったものなのでしょうか?
土佐 軍事政権を率いた3人の大統領、朴正煕、全斗煥、盧泰愚はすべて慶尚道の出身であったの対して、有力な野党政治家の金大中が全羅道出身であったため、地域対立と政治的対立がペアリングされてしまいました。私は80年代後半に全羅南道の珍島でフィールドワークをしていましたが、その地の人々は誇張なしにほぼ100%が金大中の熱烈な支持者でした。知識人の中にも「この地域対立は三国時代の百済と新羅の対立にまで遡ることのできる、非常に根深いものだ」と主張する人もいました。光州市民が標的にされた要因にもそのような側面があったことは、完全には否定できないでしょう。しかし、その後、韓国が民主化の歩みを進め、金大中が大統領に就任するに至り、そのような地域対立は解消に向かいました。慶尚道に比べ、明らかに立ち遅れていた経済投資も、それほどの格差はなくなりました。それよりは、首都圏と地方との格差のほうがずっと深刻です。
――日本の関東圏と関西圏の違いどころではなさそうですね。
土佐 済州島に対する差別は、さらに複雑なものだと言えるかもしれません。日本の沖縄の位置づけに似たところがあり、歴史的に周縁化され差別されてきた一方で、近年は観光化が進みリゾート地としての楽園や癒やしというイメージが台頭しています。そのために本当に悲惨な歴史が見えにくいものになっていますが、どちらも単一民族国家という神話を押しつけられることで固有の文化を失いつつあります。韓国は日本にも増して同質的な単一民族国家だと信じられているので、少数民族の存在とか同化できない差異というものが否定されてきました。「同じ民族」という信念が強すぎるので、差異は同化されるか、さもなければ差別され、対立の火種になるしかなかったのです。済州島の言葉は、標準語の話者と意思疎通が不可能なほど距離があるので、ユネスコの規準に従えば外国語ということになります。しかし、その差異はあくまで訛りのきつい方言という位置づけでしたから、標準語に矯正されるべきという扱いでした。結果、その話者はほとんどいなくなり、ユネスコでは「消滅の危機にある言語」に指定されています。韓国の言語学者の一部には、それを「済州語」として認定し、保護すべきと主張する声もありますが、遅きに失したといえるかもしれません。
――4・3事件は1948年4月3日、米軍占領下にある済州島で南朝鮮(韓国)の単独選挙反対を掲げた青年らの蜂起に伴い、3万人近い島民が南朝鮮国防警備隊、韓国軍、韓国警察など、朝鮮半島の李承晩(イ・スンマン)支持派らによって虐殺された事件です。
土佐 これは虐殺の規模の面でも残虐さの面でも、光州事件をはるかに凌駕しています。済州島民は、そのとき「アカ」のレッテルを貼られただけでなく、「異質の他者」として伝統的に差別されてきたことから、なおさら虐殺がエスカレートしていった面があります。この出来事を直視し、亡くなった犠牲者の鎮魂を果たすのは、もちろん簡単なことではありません。ひるがえって、いまだに関東大震災時の朝鮮人虐殺はなかったと言い張る人が日本の一部にもいるわけですから、その何十倍もの悲劇を直視することがいかに困難か、想像するのは難しくないと思います。
韓江の小説『別れを告げない(エクス・リブリス)』(白水社)はこの事件を扱った稀有な例ですが、作者自身と思われる登場人物の小説家が、虐殺について執筆しながら悪夢を見るようになることが触れられています。小説全体は虐殺に対する憎しみよりは、「愛の物語」へと昇華していくことを象徴的に描いており、それが幅広い読者に受け入れられ高く評価されました。
――小説は昔からあるようですが、映画は2010年代まではあまりなかったようですね。
土佐 映画というメディアでこの出来事を描ききるのは、さらに難しいでしょう。2014年に『チスル』という映画が制作され、インディペンデント映画としては韓国内で異例のヒットを記録し、またサンダンス映画祭でワールドシネマ・グランプリを受賞しました。モノクロ画面を通じて淡々と描き出される映像世界は、素朴な農民の日常と残虐な兵士の行動とのコントラストによって非現実的な緊迫感をかもしだしており、それはまるで出来事の真実の意味に到達できないもどかしさを表しているかのようでした。こうした表現の模索は、これからまだまだ続けられるのだと思います。
韓国の負の歴史を理解するための作品群
――光州事件と4・3事件を理解するうえで、これらを描いた作品でオススメするものはありますか?
土佐 入りやすいのは、映画でしょうね。『光州5・18』も『タクシー運転手 約束は海を越えて』も優れた映画ですが、後者のほうが外国人には入りやすいかもしれません。4・3事件は、韓国社会としてまだ消化しきれていない部分が大きく、どの作品がどうという段階に達していないので、引き続き見守り続けたいと思っています。
――ポップカルチャーで今も言及されているこれらの事件ですが、日本人はどのようにこれらを受容すれば良いのでしょうか?
土佐 特別な構えはしないで、ただ普通に人間として受け止めればいいのではないでしょうか。ポップカルチャーにまで悲惨なテーマが好んで描かれていることに、不思議に思う人もいるかもしれませんが、どの社会でも人間の弱さや歴史の悲惨さに目を向けるのは、表現者の必然です。人間はかならず間違う存在ですし、どんなに大きな力を持つ個人であっても、かならずいつか弱り、死んでいくわけですから、負の側面こそが人間の普遍的な本質だといっても過言ではありません。ただ、人生は悲惨だからこそ、せめて小説を読んだり映画を観たりする間はそのことを忘れたいと思う場合もあるでしょうし、それはそれでいいのではないかと思います。韓国にもそういう気楽な娯楽はあふれていますし、それを楽しんで悪い理由はありません。それでも、やはり人間の弱さに向き合わないといけない瞬間というものは誰にでも訪れるため、そういうときに文学は魂の大きな指針になってくれます。どんな悲惨な出来事を扱っても、優れた文学であれば加害者と被害者の対立にとどまらない深い境地まで導いてくれるので、そこには苦しみだけでなく一種の魂の浄化が含まれているものです。
――BTSやBLACKPINKなどK-POPはもちろんのこと、2020年に映画『パラサイト 半地下の家族』がアカデミー賞の作品賞を受賞、Netflixでは『梨泰院クラス』や『イカゲーム』を筆頭に多くのK-ドラマが人気を博しましたが、今回の韓江氏のノーベル文学賞受賞で韓国文学(K-文学)ブームは今後どうなっていくと思いますか?
土佐 Netflixが代表する新たなメディア・プラットフォームは、大資本を動員してグローバルな規模でそうしたメディアミックスを拡大していく方向にあります。在日コリアン一家の移民史を韓国系アメリカ人作家のミン・ジン・リーが描いた小説『パチンコ』がアメリカでベストセラーを記録し、その後Apple TV+でシリーズドラマ化されているのもその一例です。
そういったグローバルなメディア・プラットフォームにおいてドラマシリーズに映画製作を超える資本が投入されているのを見ると、ドラマと映画という区分ももう無効になっています。その中で韓国の文学や映画もまた、成長を続けることでしょう。皮肉ではありますが、矛盾や葛藤に満ちた韓国の現代史は、普遍的なドラマを作り出す格好の素材を提供してくれます。
――最後に土佐さんがこれから韓国文学を読みたいと考えている者にオススメする作品を教えてください。
土佐 日本には韓国文学の翻訳本がふんだんに存在するため、まず紹介文をのぞいてみて、気に入ったものから読み始めたらいいでしょう。私個人としては、これを機に在日コリアンの文学にも目を向けてもらいたいと願っています。金石範の小説『火山島』は、韓国で4・3事件がタブーだった時代に、在日の作家だからこそ書き続けることができた大作です。それ以外にも、李恢成、梁石日、柳美里など優れた作家の作品が多数存在します。彼らは日本文学の伝統を豊かなものにしただけでなく、日韓の架け橋となり、東アジアの民主化に独特の貢献をしてきたといえます。今回の韓江のノーベル文学賞受賞は、そうした見えない連帯のネットワークが勝ち取った部分もあるのではないでしょうか。
(構成:サイゾーオンライン編集部)
土佐昌樹(とさ・まさき)
1958年、愛知県生まれ。文化人類学者。東アジアの現実をグローバルな視点から探求することを目指して、多様なテーマに取り組む。著書に『インターネットと宗教』(岩波書店)、『変わる韓国、変わらない韓国』(洋泉社新書)、『アジア海賊版文化――「辺境」から見るアメリカ化の現実』(光文社新書)、『韓国社会の周縁を見つめて――村祭・犬食・外国人』(岩波書店)などがある。共著としては『いくつもの日本Ⅶ神々のいる風景』(岩波書店)、『21世紀アジア学』(成文堂)、『越境するポピュラー文化と〈想像のアジア〉』(めこん)、『東アジアのスポーツ・ナショナリズム:国家戦略と国際協調のはざまで』(ミネルヴァ書房)などが挙げられる。
