都立全校に「生成AI」学習を導入発表⋯先進技術についていけない「教員の格差」発生
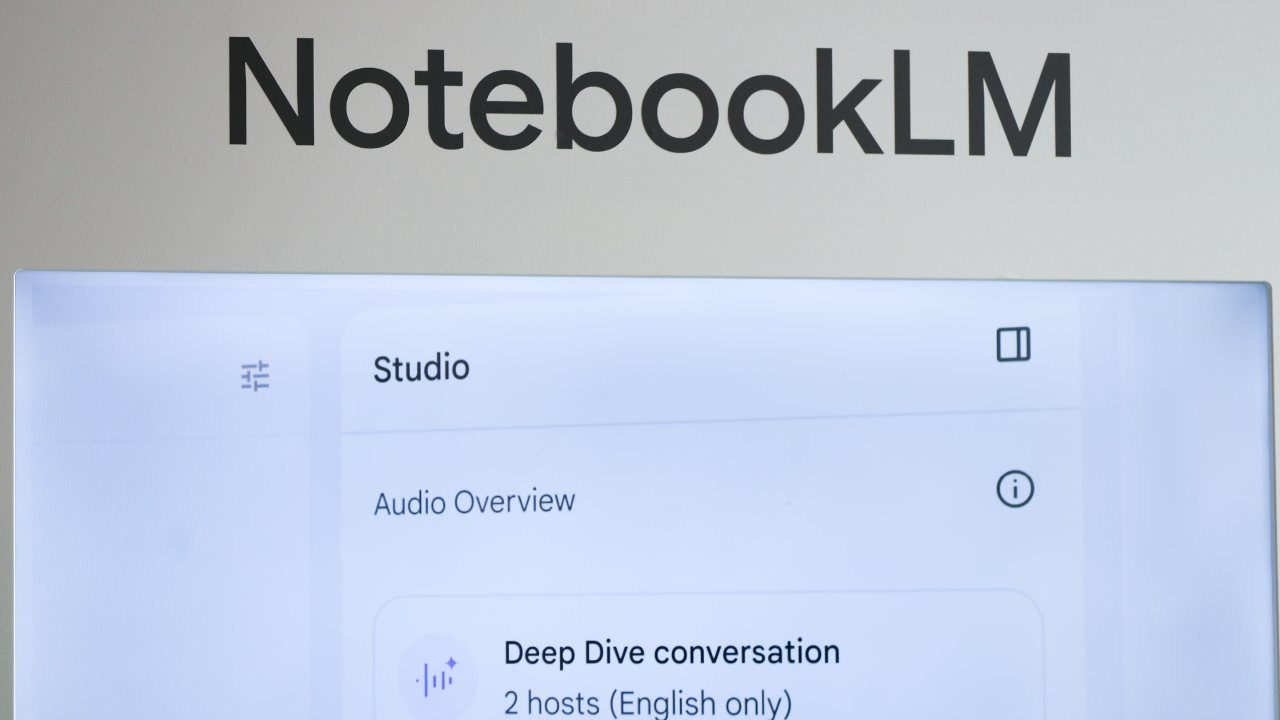
前回、NotebookLMの「音声概要」を紹介した。
NotebookLMは、アップロードしたデータについて、AIが質問応答し、要約し、アイデア出しを支援するものだ。そこに「音声概要」という機能が新たに実装された。男女の掛け合いでポッドキャスト風にデータの概要をまとめてくれる。この「音声概要」では、最後に「問い」を投げかけてくることがある。このセンスがなかなか良い。
Fラン大の授業はbe動詞から?
さらには、「学習ガイド」という機能があり、2〜3文で解答できるようなクイズを作ってくれる。エッセイ形式の質問も2〜3つ作ってくれるし、主要な用語の簡単な解説もある。これを学校の授業に使わない手はない。
一方、いま、高校では「探究」といった学び方で、「日本史探究」「理数探究」「古典探究」などの科目が設置されている。
そうした中、「総合的な探究の時間」といった授業も設けられた。各教科科目だけでは学べないこと、教科横断のテーマなどを学ぶのだ。
例えば、チームを組んで、あるテーマから課題を設定して解決を図るような「プロジェクト学習」や、自分の興味関心を掘り下げてリサーチする「リサーチ・クエスチョン」などを通して「学び方」を学ぶ。
ところが現場では、教員自身がこうした学び方を「経験していない」と感じており、教えることへの戸惑いが先行している様子が見られる。
実のところ「探究(探求)」という言葉自体は、もともと普通名詞として存在するもので、「さぐり、きわめる」ことに過ぎず、本来はそれほど身構えるような概念ではない。にもかかわらず、多くの教員がその“教え方”に迷っているのが実情だ。
背景には、近年の教育現場で「覚えるべきことを整理して教える」スタイルが主流になっていたことがある。そのため、「どう考えるか」に焦点を当てる探究型の授業が、感覚的に遠いものに感じられているのだろう。
“なにを覚えるか”に重点を置き、試験での得点をゴールとするような授業は、もはや過去のものになりつつある。それでもなお、従来型の授業スタイルが根強く残っている結果、学校ごと、教員ごとに「探究格差」が生まれてしまっている。
こうした授業改善に取り組む教員と、取り組めない教員・取り組まない教員がいることが、今の学校の大きな課題である。授業を変え続けようとする教員は、常に新しいものを試してみる。
すでにNotebookLMの「音声概要」やChatGPTを活用しながら、先進的な授業を展開している教員も少なくないだろう。しかし、そうした教員が目立てば目立つほど、「改善したい」という意欲はあっても、うまく一歩を踏み出せない教員にとっては、かえって気後れしてしまい、授業改善に取り組めない理由になってしまう。
さらに、最初から授業改善に関心のない教員は、こうした動き自体を無視し続けるだろう。そうした教員の中には、日常的には生成AIを活用しているにもかかわらず、授業では全く使おうとしないケースも見受けられる。このような教員の姿勢の違いが、授業改善の進展を妨げる要因のひとつになっている。
そして、この「教員の3層構造」は学校改革、教員の働き方改革の阻害要因になっている。
さらに、そもそも校長ら管理職がこうした生成AIを使ったことがない、あるいは使おうとせず、その利便性や活用のイメージが浮かばないことが最大の改善のネックになるケースも少なくない。
そこで、私の過去の記事( https://cyzo.jp/society/post_383480/ )をNotebookLMで「音声概要」を作ってみた。まだまだ日本語をうまく扱えない部分はあるが、これをきっかけにキャリア教育の授業をしてみてはどうか。
https://notebooklm.google.com/notebook/c7c14698-7a2e-41fd-9279-2157fde3658f/audio
「探究」は、「生徒が問いを立てることから始まる」という人がいるが、そうとは限らない。問いが立てばもっと知りたくなる、もっと考えたくなるだけのことだ。むしろ、問いが生まれるようなテーマ設定、課題提示が必要である。良いインプットが良いアウトプットを生む。
そのために、実験的に、過去記事を「音声概要」にしてみたのだ。
最初の問いは教える側が与えても良いのだ。その問いをきっかけに、生徒個々人が問いを連鎖させていけば良い。教員は生徒の答えに「どうして?」と問えば良い。そうすれば、問いが問いを呼び、問いは連鎖し始める。
頭ごなしに「問いを立てろ」というのは「問いハラ」(問いハラスメント)に過ぎない。学び方の本質を見極めたいところだ。
そうした中で、東京都は都立全校に「都立AI」を導入することを発表した。なかなか迅速な動きである。世界的に見ても早いほうではないか。 「全都立学校で生成AIを活用した学習が始まります!」(2025年5月12日 教育庁総務部デジタル推進課発表)
ただ、こうしたときに前述のような教員の3層構造を崩すことができるだろうかが鍵となる。これが構造を壊す契機になることが望ましい。
そして、こうした動きに大学はどのように対処するのだろうか。
(文=後藤健夫/教育ジャーナリスト)


